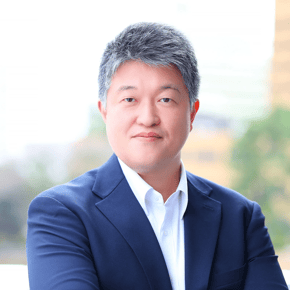シリーズ第7回となる今回は、これまで見てきた変革の波が、最も劇的な形で現れている商社業界に注目します。情報の非対称性が失われた今、商社がどのように顧客との新しい関係を築き、競争優位性を確立するかが問われています。
はじめに:迫られる根本的な問い
「お客様から『御社だからこその提案を』と言われることが増えてきた」
「既存の取引関係だけでは、新しい価値を生み出せなくなってきている」
「デジタル化で情報へのアクセスが容易になる中、商社の存在価値をどう示していくべきか」
これらの声は、多くの商社が直面している新たな局面を表しています。これまでの「つなぎ役」としてのビジネスモデルから、より高度な価値創造が求められる時代へ。その転換期において、商社は今、新たな挑戦を求められています。
目次
TABLE OF CONTENTS
1. 商社ビジネスの変革
既存モデルの崩壊
商社ビジネスの根幹を支えてきた「情報の非対称性」が、急速に失われつつあります。かつて商社は、売り手と買い手の間に立ち、双方の情報を把握することで価値を生み出してきました。例えば、「この商品をこの価格で売りたい売り手」と「この価格なら買いたい買い手」の情報を把握し、そこに適切なマージンを上乗せすることで、ビジネスが成立していたのです。
しかし今、この構造が根本から揺らいでいます。インターネットの普及により、かつては商社にしかアクセスできなかった情報の多くが、誰でも容易に入手可能となっています。世界中の市場価格がリアルタイムで把握でき、取引先の情報も瞬時に検索できる。「情報を持っているから価値がある」という商社の前提が、完全に崩れ始めているのです。
さらに深刻なのが、取引構造そのものの変化です。
- グローバルな直接取引が容易に
- プラットフォーマーの台頭による商流の変化
- 新規参入者による市場の攪乱
この結果、中間マージンの確保が著しく困難になっています。価格の透明化が進み、取引コストも低下する中、新規参入者との競争も激化。従来型の「仲介」ビジネスの収益性は、確実に低下しているのです。
デジタル化の波
さらに大きな影響をもたらしているのが、デジタル化の波です。プラットフォームビジネスの台頭は、伝統的な商社機能を大きく脅かしています。
JETROの報告によると、プラットフォームの利用者数は世界的に年々増加しており、そのうち半数近くを世界的大手のAmazonやアリババが占めていることがわかります。
EC小売市場規模は前年比10.0%増の5兆8211億ドル。直近で使った越境ECは「Amazon」「アリババ」「SHEIN」「Temu」 | ネットショップ担当者フォーラム
これらのプラットフォームは、取引の場を提供するだけでなく、決済、物流、在庫管理まで一括して提供しており、しかも、そのコストは従来の商社を介した取引よりもはるかに低いのです。
さらに、業界特化型のプラットフォームも次々と登場し、専門商社の領域にも進出を始めています。例えば、特定の産業資材に特化したマーケットプレイスなど、これまで専門商社が得意としてきた領域にも、デジタルプレイヤーの参入が相次いでいます。
2. 現場で起きている混乱
営業現場の危機感
「昨日まで当たり前だと思っていた商社の価値が、今日には全く通用しなくなっている」――。 営業の最前線では、このような危機感が急速に広がっています。
最も深刻なのが、従来の強みの効力低下です。商社の営業担当者は、長年にわたって築き上げてきた情報力と人的ネットワークを武器に活動してきました。
「この商品の市場動向はこうなっている」「この価格帯なら需要がある」「この企業の技術力はここまで来ている」。こうした情報を独占的に把握し、提供することで、その存在価値を示してきたのです。
しかし今、その優位性が急速に失われています。インターネットの普及により、市場動向や価格情報は誰でも瞬時に入手可能。取引先の技術力も、ウェブサイトで詳細に公開されています。「情報を持っているから話を聞いてもらえる」という従来の営業スタイルが、完全に通用しなくなってきているのです。
さらに深刻なのが、取引先の変化です。多くの企業が直接取引を志向し始めており、「つなぎ役」としての商社の価値が問われています。「なぜ商社を介する必要があるのか」「商社が介在することで、どのような付加価値が生まれるのか」。こうした本質的な問いかけに、明確な答えを示せない営業担当者が増えているのです。
一方で、顧客からの要求は高度化する一方です。
- より専門的な提案を求められる:商品知識だけでなく、業界動向や技術トレンドまで
- リスクテイク機能(=不確実性や損失の可能性を受け入れつつ、成長や利益を目指して意思決定する能力や仕組み)への期待:単なる仲介ではなく、責任ある関与を求められる
- コンサルティング的なアプローチ:顧客の経営課題に踏み込んだ提案が必須に
このように、商社に求められる機能は、従来の「仲介」から「価値創造」へと大きく変化しています。しかし、長年「仲介」を主業務としてきた営業担当者にとって、この転換は容易ではありません。必要なスキルも、求められる知見も、従来とは大きく異なるからです。この要求と現状のギャップを、いかに埋めていくか。それが今、営業現場に突きつけられた最大の課題となっているのです。
組織としての戸惑い
人材育成
この危機感は、組織全体にも波及しています。特に深刻なのが人材育成の課題です。
従来の商社では、若手育成の明確なモデルが存在しました。まずは定型的な取引で基本を学び、徐々に複雑な案件を任されていく。先輩の商談に同行し、交渉の仕方や関係構築のコツを学ぶ。このような段階的な育成モデルが、世代を超えて機能してきたのです。
しかし今、このモデルは完全に機能不全に陥っています。
- 定型的な取引そのものが減少
- 先輩の経験が現状にそぐわない
- デジタルスキルの習得が急務に
特に若手の戸惑いは深刻です。「先輩の仕事を見ても、自分の将来像が描けない」「求められるスキルが従来型の商社マンとかけ離れている」。こうした声が、頻繁に聞かれるようになっています。
ビジネスモデルの転換
また、ビジネスモデルの転換も待ったなしの課題です。新規事業領域の開拓は急務ですが、その判断は極めて困難です。「この分野は将来性があるのか」「どの程度の投資が必要か」「いつ収益化できるのか」。こうした本質的な問いに対する答えを見出せないまま、多くの商社が試行錯誤を続けているのが実情です。
なぜこれほど判断が難しいのか。その背景には、商社特有の構造的な課題があります。これまで商社は、既存の取引関係の中で新規ビジネスの種を見出してきました。つまり、取引先との関係性の中から、自然と新しいビジネスチャンスが生まれてくる構造だったのです。
しかし今、その方程式が成り立ちません。既存の取引関係自体が希薄化する中で、まったく新しい領域に踏み出す必要性に迫られています。それは、これまでの商社には蓄積のない分野であり、過去の経験則が通用しない世界です。さらに、デジタル技術の進化により、ビジネスモデルの陳腐化のスピードも加速しています。
このように、「どの分野に進出すべきか」という判断自体が極めて困難な中で、限られた経営資源をどう配分すべきか。多くの商社が、その答えを見出せずにいるのです。
3. 生き残りをかけた変革の方向性
新たな付加価値の創造
このような危機を乗り越えるために、商社には新たな付加価値の創造が求められています。その核となるのが、専門性の徹底的な深化です。
従来の「つなぎ役」から、特定分野の深い知見を持つ「プロフェッショナル」への転換。これは単なるスローガンではなく、ビジネスモデルの根本的な転換を意味します。商社がこれまで築いてきた広範なネットワークと、分野を絞り込んだ深い専門性。この二つを組み合わせることで、新たな価値創造が可能となるのです。
具体的には、以下のような取り組みが不可欠です。
- 業界知識の体系化と技術的知見の蓄積
長年の取引を通じて得られた暗黙知を、組織の知的資産として体系化。さらに、先端技術動向の理解や専門的な技術知識の獲得により、より高度な提案を可能に。
- 独自のソリューション開発
業界固有の課題に対して、独自の解決策を提供。これは単なる商品の組み合わせではなく、商社ならではの視点で開発された、オリジナルの価値提案を意味します。
- 顧客の経営課題に踏み込んだ提案力
表面的なニーズではなく、その背景にある本質的な経営課題を理解し、解決策を提示する能力の確立。
特に注目すべきは、リスクマネジメント機能の高度化です。グローバル化が進む中、以下のような領域で商社の機能が新たな価値を生み出す可能性があります。
- 与信管理の高度化
- グローバルな信用情報の収集・分析
- AIを活用したリスク評価
- 業界特有のリスク要因の把握
- サプライチェーンの最適化
- グローバルな調達網の構築
- 地政学リスクを考慮した供給体制の確立
- 環境負荷を考慮したサステナブルな調達の実現
このリスクマネジメント機能は、商社が長年の取引を通じて培ってきた独自の強みです。デジタル化が進んでも、グローバルな与信管理やサプライチェーンの最適化には、現地での経験や業界特有の知見が不可欠です。この領域こそ、商社が新たな付加価値を生み出せる可能性が高い分野といえるでしょう。特に近年の地政学リスクの高まりや、サステナビリティへの要求の高まりを考えると、こうしたリスクマネジメント機能の価値は、今後ますます高まっていくと考えられます。
デジタル技術の活用:現場の挑戦
デジタル技術を「脅威」ではなく、新たな価値創造の機会として活用する動きが、商社の現場で広がっています。特に注目すべきは、次の3つの領域です。
- 取引データの戦略的活用
- 業界の成長機会やリスクの予兆を早期発見
- 需要予測の精度向上による在庫最適化
- 取引パターンの分析による新規ビジネス機会の発掘
- リスク管理の高度化
- AIを活用した与信判断の客観化
- 市場リスクの定量評価
- 人間の判断とAIの最適な組み合わせ方を模索
- 業界特化型プラットフォームの構築
- 取引機能に加え、業界固有の課題解決の場を提供
- 専門的な情報共有の促進
- 新たな商流の創出
このように、デジタル技術の活用は、すでに商社のビジネスモデルを大きく変えつつあります。しかし、重要なのはツールの導入だけではありません。商社が持つ業界知見、リスク管理能力、グローバルネットワークといった強みと、デジタル技術をいかに組み合わせるか。そのカギを握るのは「人」です。デジタルスキルと専門性を併せ持つ人材の育成、ベテランの知見のデジタル化、若手のデジタルネイティブとしての感性の活用。これらを総合的に進めていくことで、商社は真の「デジタル時代のプロフェッショナル」として進化していけるはずです。
まとめ:問われる商社の覚悟
商社の現場では、「情報があれば会ってくれた」時代から、「その情報ならネットにある」時代への変化に直面しています。若手は将来像を描けず、ベテランは経験が通用しなくなり、現場からは戸惑いの声が絶えません。
しかし、顧客が本当に求めているのは、単なる情報や取引の仲介ではありません。複雑化するサプライチェーン、厳格化する環境規制、先の読めない地政学リスク——。こうした難しい課題に対して、デジタル技術も活用しながら、実践的な解決策を提示できるプロフェッショナルです。
この変革に、もう猶予はありません。ただし、一足飛びの改革は現実的ではないでしょう。今日からできることは、目の前の顧客の課題に、これまでの知見とデジタルの力を組み合わせて向き合うこと。その一つ一つの積み重ねが、結果として商社の新しい価値を創造していくはずです。
次回、最終回となる「なぜ今、BtoB企業にマーケティングが必要なのか」では、これまでの内容を踏まえ、マーケティングがどのように解決策となり得るのかを掘り下げていきます。
▼次世代BtoB営業シリーズ全8記事
次世代BtoB営業①|BtoB企業の構造改革:下請けモデルからの脱却を迫られる日本企業
次世代BtoB営業②|SIer業界 ―クラウド時代の新たなビジネスモデル―
次世代BtoB営業③|製造業 ―EVシフト、デジタル化の波に飲み込まれないために―
次世代BtoB営業④|医療営業― デジタル時代における価値提供モデルの再構築―
次世代BtoB営業⑤|ルートセールス ―デジタル時代に求められる営業改革とは―
次世代BtoB営業⑥|無形商材営業 ―価値の可視化がカギを握る時代に―
次世代BtoB営業⑦|商社ビジネス ―デジタル時代に問われる存在意義―
次世代BtoB営業⑧|なぜ今、BtoB企業にマーケティングが必要なのか