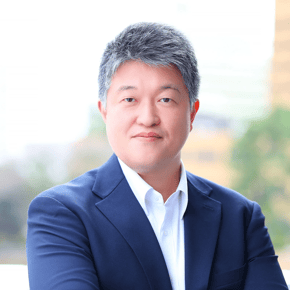「最近、SFAとか営業DXとかやたらと聞くけど…本当に必要?」
「今までExcelでなんとかなってたし、結局SFAって手間が増えるだけなんじゃ?」
こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
確かに、長年営業をやってきた現場では、Excelやスプレッドシートで案件管理をしてきた会社も多いでしょう。個々の営業担当が顧客リストを管理し、経験則でうまく回っているケースも少なくありません。しかし、「案件の進捗が見えにくい」「担当者ごとにやり方がバラバラ」「データを活かせない」といった課題を感じることはありませんか?
本記事では、「SFAで何ができるのか」をわかりやすく解説するとともに、実際にSFAを活用している営業担当者たちのリアルな声もお届けします。SFAの導入が本当に必要なのか、判断する材料になれば幸いです。
目次
TABLE OF CONTENTS
SFAの定義
まず初めに、SFAとはそもそも何なのでしょうか?
SFA(Sales Force Automation)は、「営業支援システム」とも呼ばれ、営業活動の可視化・効率化を目的としたツールです。「営業の状況を“見える化”し、チーム全体の生産性を向上させるツール」と考えるとわかりやすいでしょう。
SFA・CRM・MAの違い
営業・マーケティング領域には「SFA」のほかにも「CRM」「MA」というシステムがありますが、それぞれの違いが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか?
「どれも顧客データを管理するツールじゃないの?」と思うかもしれませんが、実はそれぞれの目的や活用シーンが異なります。
|
SFA(営業支援システム) |
CRM(顧客関係管理システム) |
MA(マーケティングオートメーション) |
|
|
主な役割 |
営業活動の可視化・効率化 |
顧客との関係構築・維持 |
リード獲得・育成の自動化 |
|
機能 |
案件管理、商談履歴、タスク管理、売上予測 |
顧客情報の一元管理、問い合わせ対応、カスタマーサポート |
メール配信、スコアリング、Webトラッキング |
|
利用部門 |
営業部門 |
営業・カスタマーサポート |
マーケティング部門 |
大まかにに言うとこのような違いがありますが、実際の現場ではSFA・CRM・MAの境界線が曖昧なことが多いのも事実です。
たとえば、CRMでSFA機能を代替していたり、MAツールにSFAの一部機能が搭載されたりしているケースも増えています。営業やマーケティングの担当者であっても、使っているツールがどれに該当するのかを意識していないことも多いのです。
こうした状況を踏まえると、ツールの分類よりも「営業・マーケティングのプロセスをどこまで可視化・自動化し、データをどう活用するか」が重要になります。
つまり、システム選びのポイントは「SFA・CRM・MAのどれを導入するか」ではなく、「自社の営業組織として何を実現したいのか?」を明確にすること。その目的に合った機能を持つシステムを選び、適切に運用することが、最も効果的なデータ活用につながるでしょう。
SFAでできるようになること
営業チームの管理をする中で、「案件の進捗が見えにくい」「個々の営業がバラバラのやり方で動いていて、成果にムラがある」「売上予測を出すのに毎回データを集めるのが大変」と感じたことはないでしょうか?
SFA(営業支援システム)は、こうした営業現場の課題を解決し、チーム全体の生産性を向上させます。
従来、営業情報の管理にはExcelやスプレッドシートが使われることが多いものでしたが、データの一元化・リアルタイム更新・分析機能という点で、SFAには大きなアドバンテージがあります。
では、具体的にSFAを導入すると何ができるようになるのか、詳しく見ていきましょう。
|
項目 |
SFA |
Excel/スプレッドシート |
|
1.案件管理と進捗管理の最適化 |
案件情報をリアルタイムで更新・共有可能。ボトルネックの特定が容易 |
手動更新が必要。最新情報の把握が困難で、データの分散リスクあり |
|
2.営業の生産性向上 |
優先度管理や自動リマインダー機能により、抜け漏れ防止 |
タスク管理機能がなく、個々の営業が手動で管理する必要がある |
|
3.意思決定のスピードと精度の向上 |
データ分析や売上予測を自動化し、迅速な判断が可能 |
手動集計が必要で、分析に時間がかかる。リアルタイム性に欠ける |
|
4.営業組織のナレッジ共有 |
商談履歴・成功パターンを記録し、組織全体で共有可能 |
データが個々に分散し、ノウハウの蓄積・活用が難しい |
|
5.営業とマーケティングの連携強化 |
リード情報をリアルタイムで共有し、最適なアプローチが可能 |
マーケティングと営業の情報が分断され、フォロー漏れが発生しやすい |
1. 案件管理と進捗管理の最適化
営業活動でよくあるのが、「この案件は、今どこまで進んでいるのか?」という情報がチーム全体で共有されていないという状況です。
SFAを導入すると、すべての案件の進捗をリアルタイムで一元管理できるようになります。各営業担当が案件情報をSFAに記録することで、マネージャーはチームの動きを可視化し、どこで商談が停滞しているのかを瞬時に把握できます。
Excelやスプレッドシートとの違い
従来のExcel管理では、進捗状況を手動で更新しなければならず、リアルタイム性に欠けます。また、複数人が同時に編集するとデータが上書きされたり、最新バージョンが分からなくなったりすることも。
一方でSFAなら、案件情報がリアルタイムで更新され、いつでも最新の状況を確認できるため、意思決定のスピードが格段に上がります。
2. 営業の生産性向上
「どの案件を優先するべきか分からない」
「フォローすべき顧客を見逃してしまう」
このような悩みは、営業活動の効率を下げる大きな要因です。
SFAを活用すれば、案件ごとの優先度を可視化し、営業が本当に注力すべき案件に集中できるようになります。また、フォローアップのタイミングを自動で通知できるため、「この案件、もうすぐ決まりそうなのに、アプローチを忘れていた!」というような抜け漏れも防ぐことが可能です。
さらに、商談ごとの活動履歴がSFA上に蓄積されるため、チーム内での引き継ぎもスムーズになります。例えば、担当者が急に変わったとしても、「どんな話をしていたのか?」「顧客は何に関心を持っていたのか?」といった情報がすぐに把握できます。
Excelやスプレッドシートとの違い
Excelやスプレッドシートでは、タスク管理やリマインダー機能がないため、営業担当者が個別にスケジュールを管理する必要があります。その結果、「フォローが遅れて案件を逃してしまった」といったミスが発生しやすくなります。
SFAなら、次回アクションをリマインドしてくれるため、営業担当者の負担を軽減し、より成果の出る営業活動につなげることができます。
3. 意思決定のスピードと精度の向上
営業マネージャーは、「どの案件が受注に近いのか」「来月の売上見込みはどれくらいか」といった情報を迅速に把握したいもの。
SFAでは、蓄積されたデータを分析し、売上予測の精度を向上させることが可能です。
これにより、「この案件は成約する可能性が高い」「このチームは案件が進んでいない」といった判断が瞬時にできるようになります。
また、経営層に対しても、リアルタイムのKPIを共有できるため、データに基づいた意思決定を支援することができます。
Excelやスプレッドシートとの違い
Excelやスプレッドシートでは、データを手動で集計しなければならず、最新の売上予測を把握するのに時間がかかります。SFAなら、データが自動で更新され、リアルタイムで売上予測やKPIを確認できるため、迅速な意思決定が可能です。
4. 営業組織の属人性排除とナレッジ共有
「トップ営業が持っているノウハウを、チーム全体で共有できない」という課題は、多くの営業組織が抱えています。
SFAを活用することで、商談の成功パターンやトークスクリプトを記録し、チーム全体で共有することが可能になります。
また、過去の顧客対応履歴がすべて残るため、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎができるというメリットもあります。
Excelやスプレッドシートとの違い
Excelやスプレッドシートでは、情報が個々のファイルに分散してしまい、営業ノウハウの共有が難しくなります。
SFAなら、全ての営業活動を一元管理し、組織全体のナレッジとして活用できるため、営業力の底上げにつながります。
5. 営業とマーケティングの連携強化
営業とマーケティングがスムーズに連携できている企業は少なく、「せっかくマーケティングが獲得したリードを営業が活かしきれていない」というケースも多いものです。
SFAを導入すると、マーケティングが獲得したリード情報をリアルタイムで営業が確認できるようになり、最適なタイミングでアプローチが可能になります。
また、SFAとCRM・MAを連携させることで、マーケティング施策の成果を営業データと紐づけて分析できるため、より効果的な戦略が立てやすくなります。
Excelやスプレッドシートとの違い
Excelやスプレッドシートには、マーケティングと営業の情報が分断されやすく、リード管理の抜け漏れが発生しやすいという課題があります。
SFAを活用すれば、マーケティングと営業がリアルタイムで情報共有できるため、リードの有効活用がしやすくなります。
このように、「Excelやスプレッドシートでなんとかなっている」と感じている場合でも、「更新の手間」「情報の分散」「データ活用の限界」といった課題を感じているなら、SFAの導入を検討する余地は十分にあるでしょう。
【対談】営業の最前線でSFAはどう使われているのか?成功の秘訣とリアルな課題
ここまで、SFAを導入すると何ができるようになるのかを解説してきました。
しかし、「理論的には分かるけど、実際に営業の現場ではどのように使われているの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、実際にSFAを活用している営業チームのメンバーに集まってもらい、SFAのリアルな運用について語ってもらいました。
SFAのメリットだけでなく、「運用で苦労したこと」「どんな工夫をして活用しているのか」といった現場ならではの本音にも迫ります。
参加者プロフィール
■ インサイドセールス
松山(以下、IS松山)
新卒で証券会社に入社し、個人向けの新規開拓営業を12~3年経験。その後、損害保険会社と国際物流の業界で法人向けの新規開拓営業を計10年ほど担当。これまでBtoC・BtoBの両方の営業経験を積み重ねてきた。
イノーバに入社後は、インサイドセールスとしてIT企業を中心に営業活動に邁進中。
「とにかくお客様と話すのが大好きです!」
■ フィールドセールス
小野(以下、FS小野)
新卒で食品メーカーに入社し、食品卸やバイヤー向けの営業を約3年間担当。その後、人材業界へ転身し、人材会社およびBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング=企業の業務プロセスを外部の専門企業に委託すること)関連の案件を扱う企業で約5年の営業経験を積む。イノーバに入社後は、フィールドセールスとしてIT企業を中心に提案営業や商談クロージングを担当。
「目標数字の達成や、成約を決めきるところにやりがいを感じています!」
SFAをどんな風に使っていますか?
―今日はお集まりいただきありがとうございます。まずはじめに、営業の現場でSFAをどんな風に使っているか伺っていいでしょうか?
IS松山:
ざっくり言うと、インサイドセールスではお客様との電話の記録を残すのがメインですね。フィールドセールスの場合は、商談の記録を残すことが中心になると思います。
FS小野:
そのあたりが基本的な使い方ですね。SFAには過去の商談記録や契約履歴もすべて残っているので、「このお客様とは以前どんな話をしたのか?」をすぐに確認できるのが便利です。
加えて、商談の進捗管理や、会社全体での数字管理にも活用しています。たとえば、契約が決まったら経理担当へ制約処理の依頼をするといった業務もSFA上で行っています。
— つまり、SFAは単なる営業のためのツールではなく、部署間の情報共有や、記録の一元管理、会社全体の数字管理にも役立っているということですね。ほかに、何か活用方法はありますか?
FS小野:
ダッシュボード機能を使って、今月の営業の数字や商談数、アクションの記録を一覧で確認しています。たとえば、メールの送信件数や電話の件数などもSFAに紐づけられるので、行動記録の振り返りにも活用しています。これを見ながら、「今月の活動量が少なかった」「この週は商談が多かった」といった営業の振り返りを行っています。
IS松山:
インサイドセールスでは、顧客リストの作成やターゲットの絞り込みにも活用しています。たとえば、業種や役職ごとに絞り込んで、アプローチすべき企業のリストを作成するといった使い方をしていますね。
— なるほど、商談の記録を残すだけでなく、SFAのデータをもとにターゲットの絞り込みにも活用しているんですね。
SFAを使う上で工夫していることはありますか?
IS松山:
インサイドセールスの場合、アポが取れたらフィールドセールスへ引き継ぐので、その際に必要な情報をしっかり記録しています。特に、商談での重要なキーワードや、お客様の関心が高いポイントは抜け漏れなく残すようにしています。
自分だけが見るわけではないので、誰が見ても分かるように記録することを意識していますね。たまに「自分の言葉で書きすぎてしまう」ことがあるのですが、引き継ぎの際に分かりやすくするため、できるだけ客観的に書くようにしています。
— 具体的には、どんな情報を残していますか?
IS松山:
たとえば、あるお客様とのアポイントでは、「コンテンツ制作の外注先を変えるべきか悩んでいる」というのが最大の課題でした。こうした情報は、今後の商談の鍵になるので、しっかりメモ欄に記録しておきます。また、「どんな話をしていたか」「どんな人物だったか」といった情報も重要なので、必要だと感じたものは必ず残すようにしています。
FS小野:
僕が意識しているのは、最新情報を常に更新することですね。営業の進捗管理にもSFAを活用しているので、「この企業は今どんなフェーズにあるのか?」がすぐ分かるように入力することを心がけています。
また、GmailとSFAを連携させて、送信したメールを自動で記録するようにしています。こうすることで、「このお客様にどんなメールを送ったか?」がすぐに確認でき、対応の抜け漏れを防げるんです。
SFAのデータをどのように活用していますか?意思決定がしやすくなった場面は?
IS松山:
たとえば、「特定の業種に注力しましょう」となったときに、SFAで業種ごとにフィルタリングして、アプローチすべき企業リストを作成できます。また、「責任者クラスの方にアプローチする」と決まれば、役職情報をもとにターゲットを絞り込むことも可能です。
さらに、フィールドセールスで「今はまだタイミングではない」となった案件が、インサイドセールスに戻ってくることもあります。こうした場合でも、SFAに商談履歴やお客様の発言内容が残っているので、すぐに対応方針を決めることができますね。
FS小野:
SFA上では商談の進捗を分類していて、毎週の定例ミーティングではSFAの画面を見ながら「この企業の次の動きは?」と確認しています。こうすることで、どの案件を優先するべきかが明確になり、営業の動きがスムーズになるんです。
また、受注・失注理由を記録しているので、過去のデータを振り返って「提案のどこを改善すべきか?」を分析することもできます。
もしSFAがなかったら、どんな苦労があるでしょうか?
IS松山:
ざっくり言うと、これまで話してきたメリットのすべてが逆になる感じですね(笑)。
FS小野:
そうですね(笑)。案件の進捗管理ができなくなるし、「この企業、今どうなってたっけ?」と毎回発生する気がします。また、今すぐ顧客にならない企業は忘れられやすくなるので、せっかく関係構築したのに、次に話すときにまたゼロからになるケースが増えそうですね。
加えて、過去の商談記録がないと、「この企業は弊社のことをどの程度理解しているのか?」が分からなくなるので、商談準備にも影響が出ると思います。
— では、Excelやスプレッドシートで管理するとしたらどうでしょうか?
FS小野:
Excelのファイルが大量発生して、どれが最新の情報か分からなくなりそうですね…。また、SFAでは自動更新されるデータも、Excelだとすべて手動なので、誰かがひとつでも更新し忘れると情報が古いままになりそうです。
IS松山:
案件ごとの履歴を探すだけで、膨大な時間がかかりそうですね。SFAなら「次回のアクション」を設定できるので、リマインドが出てくるんですが、Excelだと忘れてしまうケースも増えそうです。
— やっぱりExcel管理だと、情報の最新性を保つのが難しくなるんですね。 ファイルが増えすぎると「どれが最新かわからない問題」は、どの企業でも起こりがちな課題だと思います。SFAなら自動更新やリマインド機能があるので、抜け漏れを防げるのが大きなメリットですね。
SFAを使う中で苦労したことは?どう乗り越えましたか?
— お二人は前職でSFAを使っていましたか?
IS松山:
私はSFAは使っていなかったですね。業務管理ツールは使っていましたが、あれはたぶんCRMだったんじゃないかな。イノーバに入社して初めてSFAを使うことになったので、とにかく仕様や操作を覚えることからのスタートでした。
— 覚える段階で特に大変だったことはありましたか?
IS松山:
SFAには独自の用語があるんですよね。たとえば、商談のステータスが変わるとリードの呼び方が変わるとか。その定義の違いが最初は分からず、戸惑いました。
あとは、「このデータを出したい」と思っても、「リードに紐づけてキャンペーンのレポートを出す」という手順を踏まないといけなくて、「それは一体何のこっちゃ?」と(笑)。慣れるまでには少し時間がかかりました。
— そういう「専門用語」や「操作のルール」は、最初は混乱しますよね。どうやって克服しましたか?
IS松山:
社内にSFAに詳しい人がいたのが、本当に大きかったです。
分からないことがあれば「〇〇さんに聞けば何かしらの答えが出てくる」という状況だったので、とにかくその方に質問していました(笑)。
頼れる人がいなかったとしても、「使い方のデータベース」みたいなものがあって、誰でも見られる状態になっていると使いやすくなるんじゃないかなと思います。
— なるほど、SFAをスムーズに運用するには、拠り所となるナレッジがあるかどうかが重要なんですね。 社内に詳しい人がいるのが理想ですが、外部のパートナーや導入支援サービスを活用するのも一つの手になりそうです。 小野さんはどうでしたか?
FS小野:
私は前職でもSFAを使っていました。使い方は大体一緒なんですけど、以前はtoC向けの業務で使っていたので、入力項目は全然違いましたね。過去契約の有無や面談記録、あとは活動履歴を重視していて細かく入力していました。
— SFAって、その「入力」がひとつのハードルかなと思うんですが、小野さんはその「面倒くささ」をどう克服されました?
FS小野:
克服というか、会社全体で「きちんと入力するものだ」という意識がありましたね。 ちゃんと書いていないと、他の部署の人に「この記録がないんですけど」とか普通に怒られるので(笑)。
— 意識的に入力するための時間を確保するとか、そういう工夫とかはしていましたか?
FS小野:
「面談が終わったタイミングで必ず入力する」という感じで習慣化していましたね。
まとめて後から記録しようとすると、どうしても抜け漏れが出るので、「商談や打ち合わせが終わったら、すぐに入力する」のは大事かなと思います。
— なるほど、SFAの活用には「入力の習慣化」が鍵になりそうですね。イノーバに入社してからは、SFAをどう活用するようになりましたか?
FS小野:
最初に「どこに何を入力すると今後わかりやすいか?」を話し合いました。
たとえば、ミーティングのときも「ネクストアクションは絶対入れよう」とか、共通認識を作ることを意識しました。
僕が入社した当初は、そもそも商談記録を残す文化があまりなかったんですよね。
それぞれが自分に必要な情報だけをメモしていて、次のステップや商談の要点が明確に記録されていなかったんです。だから、「どこに何を記録すべきか?」を整理することで、全員が共通ルールで運用できるようにしていきました。
もっとSFAを有効活用するために、今後どんなことをしたいですか?
IS松山:
私は、商談内容の自動文字起こし機能があるといいなと思っています。
商談の内容が自動で記録されると、抜け漏れも減るし、より正確な情報が残せると思うんですよね。ただ、おそらくコストがかかるので、すぐに導入できるわけではないと思いますが…。
— 実現できれば、情報の精度がさらに上がりそうですね。小野さんはどうですか?
FS小野:
まずは、入力項目の整理ですね。たとえば、アポの獲得経緯や業界のセグメント情報など、記録できる項目はあるものの、入力されていないケースが多いんです。ここをしっかり入力すれば、業界ごとの商談化率や受注率などの分析も可能になるので、もっとデータを活用できるようにしたいですね。
また、商談ページのレイアウトが長すぎるという課題もあります。
実は、他社のSFA運用を見せてもらったときに気づいたんですが、うちのSFAのページは1ページがやたら長くて、空白が多いんです。どこをどう整理すればいいのか、まだはっきりとは分かっていないのですが、もっとシンプルにできるんじゃないかと思っています。
―なるほど、まだまだSFAを活用できる余地があるというのがよく分かりました。今日のお話を通して、「SFAを単なる管理ツールではなく、より使いやすく、営業の成果につながるツールにしていくこと」が重要だと感じました。本日は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!
まとめ
本記事では、SFAの基本的な役割から、実際の営業現場での活用事例まで幅広く紹介しました。
SFAは単なる「商談を記録するツール」ではなく、営業活動の可視化・最適化を通じて、生産性の向上や戦略的な意思決定を支援する仕組みです。特に、Excelやスプレッドシートでは管理しきれないリアルタイム性やデータ活用の自動化が、SFAの大きな強みと言えます。
実際にSFAを活用している営業担当者の声からも、「最新情報の管理」「部門間のスムーズな引き継ぎ」「商談の優先順位付け」といったSFAのメリットが浮き彫りになりました。一方で、「入力が面倒」「運用ルールが曖昧だと活用しきれない」といった課題もあるため、組織全体での適切な活用ルールの整備が鍵となります。
もし「SFAが本当に必要なのか?」と迷っている場合は、自社の営業プロセスにおける課題を整理し、SFAが解決策となるかを見極めることが大切です。
今こそ、自社にとって最適な営業管理のあり方を考えてみませんか?