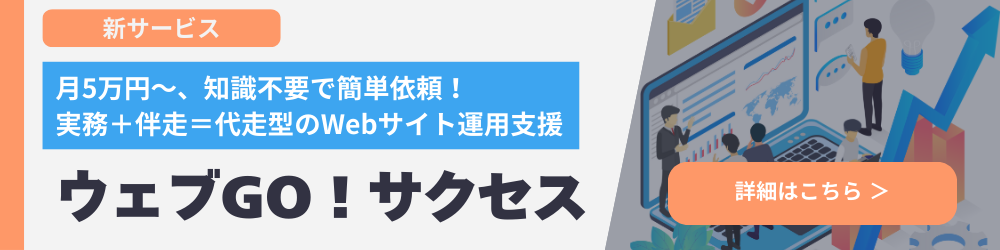Googleは2025年9月9日(日本時間)、Google検索上でAIによる回答生成機能「AI モード」の日本語版の提供を始めたと発表しました。

AI モードは、検索バーに質問を入力するだけで、AIが複数サイトを横断的に参照し、要点をまとめた回答を提示します。この体験は従来のGoogle検索とは本質的に異なるものです。
検索という行動の体験そのものが変わりつつある今、BtoB企業の情報発信にも抜本的な見直しが求められています。本記事では、検索体験の構造変化とその影響を掘り下げ、BtoBマーケティングにおいてどのように備えるべきかを考察します。
目次
TABLE OF CONTENTS
1. 「探す」から「答えが届く」へ、検索体験の構造変化
まずは、いま検索体験がどのように変化しているのか、全体の流れを整理してみましょう。
従来の検索体験
従来の検索体験は、「自分でキーワードを入力して、自分で情報を見に行く」ものでした。Google検索の結果に表示されるのは、あくまでリンクの一覧。ユーザーはその先にある複数のページを行き来し、自分の目的に合う情報を探し出し、複数の情報源を比較しながら、自分なりの「答え」を組み立てる必要がありました。
いわば検索とは、「欲しい情報を探す旅」のようなものであり、その過程でユーザーはある種の「情報検索スキル」を要求されていたのです。
2024年5月~:AI Overviews
しかし、生成AIの登場によってこの構造が大きく変わろうとしています。
2024年5月、Googleは「AI Overviews」という新たな検索機能を米国で公開し、徐々に世界中に拡大しました。これは、検索クエリ(検索エンジンに入力する言葉やフレーズ)に対して生成AIが複数の情報ソースをもとに要約を行い、検索結果の最上部に「回答のまとめ」を表示するというものです。ユーザーはリンクを選ぶ前に、おおよその結論や重要ポイントをその場で把握できるようになりました。
2025年9月現在のGoogle検索結果画面

▼関連記事
2025年5月~:AI モード(AI Mode)
AI Overviewsの延長線上で、2025年5月に米国で試験的に提供が始まったのが「AIモード(AI Mode)」です。これはAI Overviewsを含む一連の生成AI機能を、「検索時に常時オンにするモード」として提供するもので、検索画面がよりAI対話型に最適化され、初期の検索クエリに対して生成AIの回答が即座に表示され、そこから追加質問を会話形式で重ねていくことができるという特徴を持っています。
そして2025年9月、ついに日本語版の「AIモード」が公開され、日本のユーザーにも本格的な生成AI型検索体験が提供され始めました。
つまり、検索行動は「探しに行く」ものから、「答えが届き、さらに会話で深掘りする」ものへと進化しつつあるのです。キーワードを工夫したり、複数ページを比較検討したりといった従来の“検索スキル”が、今後は不要になっていくかもしれません。
検索行動の変化の流れを押さえたところで、次章からはAI OverviewsとAI モードについて詳しく掘り下げていきましょう。
2.AI Overviewsの登場で起きたこと
「ゼロクリック検索」の増加
2024年5月以降、AI Overviewsが広がるにつれて目立ってきたのが「ゼロクリック検索」です。
ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果ページに表示された要約や情報だけで満足し、リンクを一切クリックしない現象のこと。従来は検索結果のリンクをクリックして答えを探していましたが、今ではAIによる概要を読むだけで解決するケースが増えているのです。
実際、Pew Research Centerの調査によると、Google検索でAI Overviewsが表示されたユーザーは、表示されなかったユーザーと比べて、リンクをクリックする割合が低いことがわかりました。
▼AI要約が表示されると、他サイトへのクリック率が下がる
具体的には、AI Overviewsが表示された検索結果において、検索結果のリンクをクリックしたのは全体の8%にとどまりました。一方、AI Overviewsが表示されなかった場合は、その約2倍の15%がリンクをクリックしています。
さらに、AI Overviewsの中にあるリンク自体をクリックする人も非常に少なく、該当ページを訪れたユーザー全体のわずか1%にすぎませんでした。
さらに、Semrushの分析によると、AI Overviewsが表示されるのは、主に情報探索型のKnowクエリ、「なぜ〜なのか」「どうやって〜するか」を調べるInfomationalクエリで、その割合は全体の約9割を占めています。
逆に、「特定のサイトに行きたい」(Goクエリ、Navigationalクエリ)や「商品を購入したい」(Doクエリ、Transactionalクエリ)といった検索では、AI Overviewが表示される頻度は低めです。
▼AI Overviewはほとんどが「Knowクエリ」で発生している
AI Overviewsの表示が情報探索型に偏る理由
この背景にはGoogleのビジネスモデルがあります。Googleの主な収益源は検索広告であり、特に比較検討や購買に近い検索は、広告と強く結びついています。もし「商品を購入したい」(Transactional)クエリにAI Overviewsを全面的に導入してしまうと、広告クリックの機会が減り、収益に直結するリスクがあるのです。
そこでGoogleは、「ユーザーにとって便利で広告収益への影響が少ない領域」=KnowクエリからAI Overviewsを広げていると考えられます。つまり、検索体験をAIで進化させつつ、広告という収益の柱を守るという絶妙なバランスの上に成り立っている機能だと言えるでしょう。
3.AI モードとは?
AI モードによる新たな検索体験
AI Overviewの進化版とも言えるAI モードは、Google検索窓の「AI Mode」ボタンから切り替えられる、新しい検索スタイルです。これをオンにすると、従来のリンク一覧ではなく、AIとのチャット形式の画面に変わります。
▼2025年9月現在のGoogle検索画面

▼検索クエリを入力し、「AI Mode」ボタンをクリックするとAIとのチャット画面へ。
AIがまとめた概要がまず提示され、その下に参照リンクが並ぶ。

▼追加入力欄に質問を入力すると、

▼追加質問に応じた回答がさらに表示される

このように、AI モードは利便性が高い分、ユーザーが「もう答えは得られた」と感じれば、リンクをクリックしないまま検索を終えてしまう可能性が高まります。すでにAI Overviewsで顕著だった「ゼロクリック検索」が、AI Modeでもさらに広がるのではないかと懸念されています。
AI モードの仕組み
AI モードの裏側では「Query Fan-out(クエリファンアウト)」と呼ばれる仕組みが動いています。これは、ユーザーの質問を複数の小さな問いに分解し、それぞれを同時に検索してから一つの答えにまとめるというものです。
たとえば「パリ旅行のおすすめプランは?」と尋ねれば、AIは「観光スポット」「レストラン」「移動手段」など複数の観点から調べ、それを一つの提案として返してくれるのです。
▼「Query Fan-out」のイメージ
「Query Fan-out」は、一見、ユーザーの検索を先取りするような検索を行う点で、今までの検索エンジンの体験を大きく変える可能性があります。
従来もGoogle検索には「入力途中に出てくる検索候補(サジェスト)」や「関連する質問一覧(People Also Ask)」といった機能がありましたが、これらはあくまでユーザーに“次の検索”をさせるための補助でした。
一方、Query Fan-outはユーザーが入力した1つの検索から複数の角度に自動で広がり、答えそのものを提示しようとします。そのため、どのような影響が出るのかはまだ未知数であり、今後も注視が必要です。
4.コンテンツマーケティングへの影響
AI OverviewsやAIモードの登場は、検索体験そのものだけでなく、「企業のコンテンツがどう見られるか」にも大きな影響を与えます。
この変化は、私たちのマーケティング活動にどんな影響を及ぼすのでしょうか?
SEO戦略の見直しが必要に
従来の「検索 → URLをクリック → Webサイト訪問」という流れが変わりつつありますが、SEOの重要性が下がるわけではありません。検索結果やAIの要約に自社の情報が取り上げられることは、依然として露出の増加や信頼の構築につながります。
ただし注意すべきは、AIによる回答が表示される「一般的な質問型の検索」では、ユーザーが要約だけで満足してしまい、サイトに訪れないケースが増えていることです。つまり、検索全体での流入は今後減少していく可能性があります。
そのため今後のSEOは、「調べて終わりの情報探索」ではなく、「購買や問い合わせに直結する検索」に軸足を移すことが重要です。例えば、商品名での検索や見積依頼に関するクエリは、AIだけでは完結せず、必ずWebサイト訪問が必要になる領域です。検索ボリュームの大きいキーワードを対策するという従来の方針から脱却し、前述のDoクエリやGoクエリでの検索体験の向上がますます重要になってきます。
マーケティング投資の分散
SEOに依存しすぎるのはリスクが高まっています。そのため、顧客の情報ニーズに併せた様々なチャネルでの情報発信がますます重要になるでしょう。
ただし、ここで課題となるのが訪問者の「質」です。様々なチャネルで集客をすることで、多様なニーズを持った見込み顧客のリード情報を獲得することができますが、その見込み顧客の検討度合いはまちまちで、どの見込み顧客から優先的にアプローチすべきかを見定めることはこれまで以上に困難になるかもしれません。
そのため、従来以上にリードナーチャリング(見込み顧客の温度感を少しずつ高めて購買につなげること)やリードクオリフィケーション(見込顧客の温度感を見定めて選別すること)の重要性が増してきます。実際、急成長したスタートアップ企業の事例を見ると、強力なナーチャリング施策と営業体制を組み合わせることで、温度感の低いリードを効果的に受注へと転換しています。
つまり、これからは「どれだけ温度感の高いリードを集められるか」ではなく、「集めたリードをいかに育てて、優先順位をつけながら成果につなげるか」が競争力の分かれ目になります。これまでSEOを中心にWeb集客に取り組んでいた企業も、今後はマーケティング投資の優先度の変更が避けられない時代になっていくでしょう。
BtoBとBtoC、それぞれの違い
AIによる検索体験の変化は、すべてのビジネスに同じように影響するわけではありません。特にBtoBとBtoCでは、検索クエリの性質やユーザーの情報探索スタイルが大きく異なるため、受けるインパクトや必要な対策も変わってきます。
- BtoB(法人向けビジネス)
BtoBの世界は業界ごとにニッチで専門性が高く、検索されるキーワードも「製品カテゴリー×機能」や「業務課題×ソリューション」といった具体的で掛け合わせになっているもの(ロングテールキーワード)が中心です。こうした検索はAIが一言で答えを完結できるものではないため、依然としてSEOの価値は高いといえます。さらに、独自性や専門性が高いコンテンツはAIの要約に引用されやすく、企業の信頼を高めるチャンスにもなります。つまり、BtoBにおいてはSEOの「深さ」や「専門性」を武器にできる余地が残されているのです。 - BtoC(消費者向けビジネス)
一方、BtoCでは「最安値は?」「おすすめは?」「○○とは?」といったシンプルで短い検索が多く、ユーザーは短時間で答えを得たいと考える傾向があります。こうした検索はAIによる要約の格好の対象となり、「ゼロクリック検索」が増えています。そのため、Web検索経由の流入に依存しすぎるのはリスクが高まっていると言えるでしょう。SNS、YouTubeやTikTokといった動画チャネル、さらにはアプリなど、AI検索の外でユーザーと直接つながるチャネルへの投資が不可欠です。
実際、調査データでもAI Overviewsによるクリック減少はBtoC系のジャンルに集中しており、BtoBの影響は現状では全体の5%程度にとどまっています。
とはいえ、今後の拡大を見据えれば、どちらのビジネスでもです。「自社の強みがどうAIに扱われるのか」を見極め、早めに備えていくことが重要
▼BtoBよりもBtoCビジネスがAI Overviewの影響を受けている
Webサイトの役割の変化
AIが要点を要約してくれる時代において、Webサイトはただ「情報を並べる」だけでは不十分です。これからのWebサイトは、「体験を提供する場」へと進化する必要があります。
- 見積もりや問い合わせをスムーズにできる
- 個別にカスタマイズされた情報や提案を得られる
- AIチャットや動画などを活用した双方向の体験ができる
つまり、ユーザーがWebサイトを「わざわざ訪れる理由」をつくることが重要なのです。
従って、従来よりも、会員サイト的な機能や、動的に見積を提示する機能など、個別性やインタラクティブ性がWebサイトにも求められていくと考えるべきでしょう。
新しいSEOの考え方
最近では、「Answer Engine Optimization(AEO)」や「Generative Engine Optimization(GEO)」という新しい考え方も出てきています。これらは、AIに引用されやすいように、簡潔で構造化されたコンテンツを用意するアプローチです。
とはいえ、AIに最適化すること自体を目的にコンテンツを整えるのは本末転倒です。あくまで出発点は「顧客にとって価値ある情報を届けること」であることを忘れてはいけません。そのうえでAIが参照しやすい形を意識することが、従来のSEOを補強しつつ、これからの検索体験にも対応する現実的な戦略になるでしょう。
▼関連記事
生成AIで変わるインターネット検索:AIが迫るビジネスモデル変革|イノーバウィークリーAIインサイト -55
5.「Google検索」の行方
GoogleがAI OverviewsやAI モードを導入した背景には、検索市場の主導権を守りつつ、広告収益を維持するという明確な意図があります。ChatGPTやPerplexityといった新興AI検索の存在は大きな脅威であり、Googleは会話的で文脈に沿った応答を提示することで、ユーザーの習慣を「検索=Google」にとどめようとしているのです。
また、Googleは検索の利用履歴やユーザー行動データを長年にわたり蓄積しており、加えてAndroidやChromeといった自社サービスを通じて膨大な利用データを持っています。これらは生成AIの精度を高めるうえで欠かせない資産であり、新興の競合がすぐに真似できるものではありません。
今後もGoogleは、競合の動きを見据えながら「体験の進化」と「収益モデルの維持」を両立させ、検索のあり方を更新し続けていくと考えられます。
▼関連記事
Googleの牙城を狙う新世代「AIブラウザー」|イノーバウィークリーAIインサイト -61
6.まとめ:変化に備えるために
AI OverviewsやAI モードの登場により、検索体験は「探す」から「答えが届く」へと大きく進化しました。この変化は、単にSEO施策の調整にとどまらず、マーケティング全体の設計を見直す契機となっています。
検索のルールは変わっても、顧客が「価値ある情報を求める」本質は変わりません。AI時代の検索を脅威と捉えるのではなく、新しい接点としてどう活かすか。それが今後のマーケティングの成否を大きく左右するでしょう。
▼参考記事