デジタル化が加速し、情報があふれる現代。
企業にとって、自社の存在感を示し、顧客との絆を深めるチャンスは無限に広がっています。自社の強みを活かし、顧客に響く価値ある情報を届けるには、戦略的なコンテンツマーケティングが不可欠です。
本記事では、「コンテンツ制作の本質的な意義」から、実践的なノウハウまでを体系的に解説します。さらに、数多くのBtoB企業のコンテンツ制作を成功に導いてきた弊社のプロフェッショナルによる、現場視点での深い知見もお届けします。基礎となる考え方から、実践的なポイントまで、必要なエッセンスは全てここに。きっと、今後の道標となるはずです。
目次
TABLE OF CONTENTS
コンテンツ制作とは?その目的と重要性
コンテンツ制作の目的
コンテンツ制作とは、企業や組織が自社のウェブサイトやSNS、メールマガジンなどのメディアで発信する情報を作成することです。しかし、それは単なる情報発信ではありません。見込み客の意思決定を支援し、最終的な成約につなげるための重要なコミュニケーション活動なのです。
コンテンツ制作には、短期的な目標と長期的な目標があります。短期的には見込み客の獲得や問い合わせの促進、長期的にはブランド構築や市場での信頼確立を目指します。具体的な目的は以下の通りです。
- ブランド認知の向上
- 専門性・信頼性のアピール
- 潜在顧客の掘り起こし
- 顧客との関係性の構築
- 商品・サービスの訴求
これらの目的は個別に存在するのではなく、相互に関連し合っています。例えば、専門性のアピールは信頼性の向上につながり、それが顧客との関係性構築を促進します。そして最終的には、商談や成約といったビジネス成果へと結びつくのです。
このように、コンテンツは見込み客の検討プロセスに沿って、適切なタイミングで必要な情報を提供する役割を果たします。特にBtoB製品のような検討期間の長い商材では、この段階的なアプローチが重要となります。
なぜコンテンツ制作が重要なのか
インターネットやスマートフォンの普及により、消費者の情報収集の方法は大きく変化しました。今や多くの人が、商品やサービスを購入する際には、まずウェブサイトで情報を探します。企業がウェブ上で積極的に情報発信をしていなければ、顧客に選んでもらえる機会を逃してしまうでしょう。
特に、BtoBビジネスにおけるコンテンツの重要性は増す一方です。かつての営業活動は、製品説明から始まることが一般的でした。しかし今や、見込み客は商談の前に十分な情報収集を済ませています。つまり、コンテンツの質が、商談に進むか否かを左右する重要な要素になっているのです。
また、コンテンツ制作は、長期的なブランディングにも欠かせません。一時的な広告とは異なり、コンテンツはウェブサイト上に蓄積され、長期間にわたって顧客との接点を作り続けます。高品質なコンテンツを継続的に発信することで、企業は自社のブランドイメージを確立し、顧客からの信頼を勝ち取ることができるのです。
▶関連記事:BtoBブランディングについてのシリーズ記事を読む
コンテンツ制作の種類と特徴
コンテンツには様々な種類があり、それぞれ目的や特徴が異なります。重要なのは、各コンテンツの特性を理解し、見込み客の検討段階に合わせて適切に使い分けることです。代表的なコンテンツとしては、以下の4つが挙げられます。
1.ブログ記事
ブログ記事は、最も一般的なコンテンツの形式です。企業のウェブサイトに設けられたブログで、業界の動向や自社の取り組み、商品・サービスの活用方法など、様々なトピックについて発信します。
ブログの大きな特徴は、検索エンジン経由での流入を狙えることです。狙ったキーワードで上位表示させることで、多くの潜在顧客を呼び込むことができます。
また、記事を通じて見込み客を段階的に育成できることも、ブログの重要な特徴です。見込み客の検討段階に応じて、記事の深さや専門性を変えることで、効果的な情報提供が可能になります。例えば、
|
課題認識段階 |
業界の課題や動向を解説する概論的な記事 |
|
情報収集段階 |
具体的な解決方法や事例を紹介する実践的な記事 |
|
比較検討段階 |
自社ソリューションの特徴や強みを解説する記事 |
このように段階に応じたコンテンツを用意することで、見込み客は自身の関心や理解度に合った情報を得ることができ、無理なく検討プロセスを進めることができます。さらに、どの段階のコンテンツがよく読まれているかを分析することで、見込み客の関心度合いや検討状況を把握することも可能になります。これは営業活動の優先順位付けにも活用できる重要な指標となるでしょう。
2.ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、特定のテーマについての問題提起や、解決策の提示を行う報告書形式のコンテンツです。ブログ記事よりも専門的で、内容が濃いのが特徴です。
主な目的は2つあります。
- 自社の専門性・信頼性の証明
- 質の高いリードの獲得
企業が自社の専門性を示し、リードの獲得を目的としてホワイトペーパーを作成するケースが多くあります。多くの場合、問い合わせや資料請求のためのフォームと組み合わせ、見込み客の情報を取得します。
ホワイトペーパーの効果を最大化するためには、以下の3つのポイントが重要です。
- 具体的な数値やデータを含め、説得力を高める
- 自社の独自の知見や研究結果を盛り込む
- 読者が実践できる具体的なアクションプランを提示する
これらの要素を含むホワイトペーパーを作成し、資料ダウンロード時に問い合わせフォームを設置することで、検討度の高い見込み客の情報を獲得できます。ただし、一般論に終始せず、自社ならではの視点や知見を示すことが重要です。
3.動画コンテンツ
動画は文章では伝えきれない非言語情報も含めて発信できる点が強みで、商品の紹介や、会社案内、CEOメッセージなど、様々な場面で活用できます。
特にBtoB分野では、以下のような活用方法が効果的です。
- 製品やサービスの具体的な使用シーン
- 導入企業の担当者インタビュー
- 技術的な解説や使い方のチュートリアル
これらの動画は、営業活動の補助ツールとしても活用できます。
4.インフォグラフィック
インフォグラフィックは、情報やデータをビジュアル化して表現するコンテンツです。グラフやチャート、イラストなどを使い、複雑な情報をわかりやすく伝えるのが目的です。
テキストだけの記事と比べて、はるかに多くの情報を盛り込めます。また、読者の目を引きやすく、SNSでのシェア率も高いのが特徴です。
例えば、人材系の企業なら、以下のようなトピックでインフォグラフィックを作成できるでしょう。
- 景気動向と求人倍率の推移
- 各業界の平均年収と転職率の比較
- 働き方改革関連法の概要と企業の対応状況
もともとデータの形で存在する情報を、見やすく加工してビジュアルに表現するのがポイントです。
コンテンツの使い分けと連携
それぞれのコンテンツは独立して存在するのではなく、相互に連携させることで効果を最大化できます。例えば、
・ブログ記事からホワイトペーパーへの誘導
・動画コンテンツとブログ記事の相互補完
・インフォグラフィックのSNSでの拡散とブログへの誘導
このように、各コンテンツの特性を活かしながら、見込み客を段階的に深い関係性へと導いていくことが重要です。
コンテンツ制作の手順
では、コンテンツ制作を成功させるためには、具体的にどのようなプロセスを踏めばよいのでしょうか。ここでは、コンテンツ制作の一般的な流れを5つのステップに分けて見ていきましょう。
1. 企画・戦略立案
企画・戦略立案は、コンテンツ制作の成否を決める最も重要な工程です。以下のステップで進めていきます。
- コンテンツの目的設定(ブランディング、リード獲得など)
- ターゲットペルソナの明確化(職種、役職、課題など)
- 競合他社の分析と差別化ポイントの特定
- テーマと切り口の決定
- SEOを意識したキーワード選定
2. 取材・情報収集
次は、コンテンツの材料となる情報を集めます。
- 社内関係者への取材
- 外部専門家へのインタビュー
- 現場の見学・体験
- 文献調査とウェブリサーチ
特に事例コンテンツでは、導入前の課題、選定理由、導入効果、実際の使用感などを必ず確認しましょう。
3. 構成・ライティング
集めた情報を整理し、論理的な流れを作ります。
- 読者目線での分かりやすい説明
- 事実と意見の明確な区別
- 具体例の効果的な活用
- BtoB特有の視点(意思決定者と実務担当者双方への配慮)
4. デザイン調整
読みやすく魅力的な見た目に仕上げます。
- 画像・図表の効果的な配置
- スマートフォン対応
- SEO対策(タイトル最適化、メタ設定など)
5. 公開・プロモーション
完成したコンテンツを効果的に発信します。常にPDCAサイクルを回し、継続的な改善を心がけましょう。
- 最適なタイミングでの公開
- SNSやメルマガでの告知
- 関連記事からの内部リンク
- アクセス解析による効果測定
プロに聞く!成果を出すコンテンツ制作のポイント
ここまで、コンテンツ制作の基礎知識から実践的なノウハウまでをご紹介してきました。では、実際にコンテンツ制作を成功に導くには、具体的にどのような点に気をつければよいのでしょうか?
今回は、多彩な編集経験を持つ弊社イノーバのコンテンツ編集者3人にインタビューを実施しました。出版・新聞・Webと、異なる媒体で豊富な制作実績を持つメンバーたち。児童書編集、雑誌編集、新聞記者として培った「読み手の心をつかむ」編集力と、それぞれの業界で磨き上げた専門性を持つプロフェッショナル揃いです。今回は、そんな3人に、各業界での経験を活かしたBtoBコンテンツ制作の極意や、成果を出すためのポイントについてたっぷり語ってもらいました。
■プロフィール■
編集O:前職は編集プロダクション。子ども向け書籍の編集を15年以上担当。
編集M:これまで出版社2社と編集プロダクションで雑誌編集とライティング業務を20年、
求人サービス会社で求人コンテンツ制作のマネージャーを5年経験。
編集K:地方新聞社で編成記者と取材記者を併せて約5年経験。
質問1:「成果の出るコンテンツ」と「成果の出ないコンテンツ」の違いは何でしょうか?
編集M:
「目的に向けた想像力を働かせた内容か否か」。
具体的には「コンテンツを発信した後(発信したその先)を見ているか否か」だと個人的には考えています。
発信した後(発信したその先)を見ているコンテンツは、コンテンツをきっかけに読者(顧客)の購買促進(あるいは契約、問い合わせ)といった行動喚起につなげたいという意図があります。
一方、発信することが目的(あるいは発信して満足)のコンテンツは、自己満足的なコンテンツになりがちで、読み手には「ただの情報」として処理され、何の印象にも残らないことが多いという共通点も見られます。
編集K:
マスメディアの記事でもWeb記事でも、受け手に評価されるコンテンツには「独自性」があります。たとえば、以下のような手法で独自性を生み出すことができます。
- 鮮度の高い情報を入れる
- 特定の分野における専門性を高める
- 人とは違う斬新な視点でアプローチする
- 個人の体験や感想を入れる
- 特定の地域に話題を絞る
- 普遍的なトピックでも、複数の要素を組み合わせる
読者がスクロールする手を止めるのは、そのメディアにでしか得られない情報や体験があるはずーという期待があるからです。その期待に応えられたとき、読者の感情は動き、行動につながると考えています。
質問2:BtoB企業のコンテンツ制作で、特に気をつけていることはありますか?
編集O:
制作時にはその先にいるユーザーや読者を想定し、わかりやすいか、伝わるかを常に意識して制作しています。
編集K:
業界特有の専門用語と一般的な表現のバランスです。
メディア全体で想定読者のリテラシーを考慮しておくことはもちろん、個々のコンテンツにおいても、ターゲットとなるユーザーの習熟度によって伝え方を調整することが必要です。
ユーザーが受け取るコンテンツによってその企業の印象は大きく左右されるため、言葉の使い方にはとても注意しています。
質問3:「読者に刺さる企画」を生み出すために意識していることはありますか?
編集M:
「その情報を読者が知りたいか」「その情報は読者にとって有益か」という読者側の視点を持つこと(持ち続けること)。
発信者側がいくら「有益な情報だ」「ためになる」「面白い企画だ」と思ってコンテンツを制作しても、受け取る読者にそう思ってもらえなければ、何の効果もないコンテンツをただ垂れ流しているだけになってしまいます。
発信者する側としては、思惑(利益)もあって発信せざるを得ない情報もありますが、それが読者に響かなければ意味がないと考えています。
そういう場合は「そのままでは刺さらないので、発信せざるを得ない情報の味付けを変えたり視点を変えるなどして料理し直す」必要があります。
編集K:
人間味を散りばめることです。
たとえば、「新製品『A』を紹介するために、開発者のBさんに取材して記事コンテンツを作る」という企画を考案したとしましょう。記事の主役は製品「A」ですが、製品に関する詳細な情報を羅列するだけでは読者の関心は得られません。
開発の背景、苦労話、Bさんが個人的に気に入っている機能など、個人の主観や感情を記事に盛り込むことで、読者の共感も得られると考えています。
また、取材型記事でなくても、制作者が「面白い」と思ったポイントをしっかり伝えれば、読者に刺さるコンテンツが作れるはずです。
質問4:コンテンツの効果測定において、数値以外に注目している指標はありますか?
編集O:
数値化しにくいものとしては、ユーザーや読者の反応やブランドの影響力の変動などが挙げられるかと思います。BtoBのコンテンツ制作においては、まずはお問合せの数だけでなく、どのようなお問い合わせが多いか、SNSなどでの反応をひとつの指標にしやすいと考えます。
編集K:
自分が携わった記事が「どのように読まれるか」、さらには「どのように使われるか」は大きな関心事です。
私たちが現在携わっているメディアには、コメント欄のようなフォームは設置されておりませんので、主に被リンクを確認することが多いです。
そこで確認するのは、まずは記事の内容が正しく解釈されているか。そして、掲載先ではどのような情報がプラスされているのかをチェックし、今後の制作の参考にします。
質問5:コンテンツ制作で失敗した経験はありますか?それをもとに気を付けていることがあれば教えてください。
編集O:
当たり前ですが、ペルソナ設定とズレた専門用語の多用など、修正作業の過程で「誰」に向けて「何」を伝えたいのかを置き去りにした記事は、やはり読んでもらえないことが多いと感じました。初めの構成でしっかり基盤を固め、ペルソナに合った文章や図解、画像を用いてユーザーに寄り添ったコンテンツ作りを心がけています。
編集M:
二番煎じ、見切り発車、ストーリー性のない詰込みコンテンツなどは失敗する確率が高いと経験則では感じています。
とくに「ストーリー性のない詰込みコンテンツ」は、言葉足らずの内容になることも多く、自分自身では理解していても相手には伝わらない内容になることが往々にしてあります。
そのため気を付けていることは、繰り返しになりますが「読者視点」です。
コンテンツ制作者は「神の目線」になる危険性を常にはらんでおり、読者を置いてけぼりにする「言葉足らずな内容」や「無理な情報詰込み」を犯しがちなので、そうならないように注意しています。
質問6:AIの登場でコンテンツ制作に起きている変化は何でしょうか?注意していることはありますか?
編集M:
AIが手軽に使えるようになり、プロや専任担当者でなくても、ある程度のクオリティの記事やコンテンツが制作できるようになったのは間違いありません。
その一方で、実際の現場では、AIに対して「AIは人間が使う便利なツールであって、AIに左右される(使われる)側にならない」という認識で一致していると思っています。
いわば、「AIの回答は参考程度に利用する」くらいの距離感です。
文章においては、人間が書いたものか、AIが作成したものか、見分けがつかないところまでAIは進化していると感じることもあります。
しかし、やはり最後のエッセンス(文章に魂を宿らせる役割)はいまだに人間の発想領域であり、人の必要な役割だと思っているので、ワードチョイス(言い回し)を含めて頼り過ぎない(AIに引っ張られない)よう注意しています。
編集K:
企画立案からアウトライン制作、執筆、校閲まであらゆる段階において生成AIは活用できます。気付けばAIを使っていない日はないくらいです。
ただ、AIが生成した内容をコンテンツに採用するかどうかは自分で判断していますし、実際の採用率も1,2割という感覚です。
注意していることは、
- AI回答が理想から離れている場合は、早めに見切りをつける
- 発想を縛られないために、最初は自分の頭で考える
です。
▶関連記事:AIを活用したコンテンツ制作のコツについて記事を読む
質問7:最後に、これからコンテンツ制作に取り組む企業へのアドバイスをお願いします。
編集O:
コンテンツは、企業とユーザーをつなぐ重要な役割を担うものだと思います。ユーザーとの距離を縮めるための情報発信はもちろん、ユーザーの意見や反応を取集することで、ユーザーのニーズの理解につながります。
また、ユーザーの意見をコンテンツ制作にも活かすことで、企業への理解が深まり、結果CV率の向上につながると考えられます。
編集M:
AIツールの活用が広がっていますが、その一方で、制作したコンテンツを届ける先は、依然として読者や顧客など心や感情を持つ「人」であり、それは今後も「最終決定を下すのが人である限り」変わらないと考えています。
そのため、自社が制作したコンテンツの受け手は、あくまで「人」であり、「人」を相手にコンテンツを作るという制作者の意識は大切です。
最終的にはコンテンツに制作する人間のエッセンスが感じられるか否かは、コンテンツで人の心を動かすうえで非常に重要なポイントだと思っています。
コンテンツは、使いようによって事業の特効薬にもなれば、ベクトルを誤ると毒にもなり得るものだと個人的には思っているので、常に顧客(読者)を意識することをおススメします。
編集K:
コンテンツの役割は、「マーケティングツールの一つ」に留まらず、業界や社会を支える「知識の基盤」でもあります。課題を抱えるユーザーの目線に立ち、皆様がお持ちの知見を伝え続けてほしいと思います。
まとめ
コンテンツ制作は、企画・戦略立案から実際の制作、効果測定まで、体系的なプロセスを必要とします。その中で成否を分けるのは、「発信したその先」を見据えた戦略的な視点と、読み手に寄り添う丁寧な制作姿勢です。AIの活用が進む今だからこそ、人間ならではのクリエイティビティと、受け手の感情に響く独自性がより重要になっています。
特にBtoB領域では、専門性と分かりやすさのバランス、ユーザー企業の課題に対する深い理解が不可欠です。コンテンツは単なる情報発信ツールではなく、企業とユーザーをつなぐ重要な接点であり、業界の知識基盤としての役割も担っているのです。
目的を明確にし、ターゲットを理解し、独自の価値を提供する。この基本に忠実に、かつ柔軟に対応していくことが、これからのコンテンツ制作では求められるでしょう。
コンテンツマーケティングの戦略と手法を学ぶためにはこちらもおすすめです!
- コンテンツマーケティング時代の購買行動モデル「DECAX」を考える
- 【プロが解説】ペルソナマーケティングを学ぶならこの本がおすすめ!
- 【2024年最新】ホワイトペーパーと動画の戦略的活用術: コンテンツマーケティングの新法則
- SEOとコンテンツマーケティングの違いは?ウェブサイトの成果を出すための基礎知識と連携方法
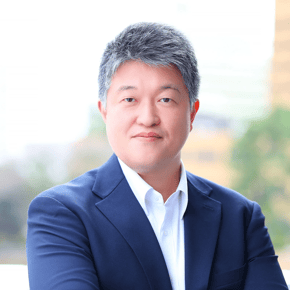
宗像 淳 / イノーバCEO
1998年に富士通に入社し、北米ビジネスにおけるオペレーション構築や価格戦略、子会社の経営管理等の広汎な業務を経験。MBA留学後、楽天で物流事業、ネクスパス(現トーチライト、博報堂DYグループ)でソーシャルメディアマーケティング事業の立ち上げを担当。ネクスパスでは、事業開発部長として米国のベンチャー企業との提携を主導した。
2011年、マーケティング支援会社である株式会社イノーバを設立、代表取締役に就任。日本におけるコンテンツマーケティング/BtoBマーケティングの第一人者として、15年以上にわたり5000社以上の経営課題やマーケティング・営業課題を分析し、幅広い業界で企業の事業成長に貢献。「事業を伸ばすには実行力が重要であり、実行力とは組織・人である」という哲学で、人にこだわった支援会社づくりに取り組んでいる。
2026年2月、最新刊『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』(インプレス)を上梓。著書に『商品を売るな コンテンツマーケティングで「見つけてもらう」仕組みを作る』(日経BP社)、『いちばんやさしいコンテンツマーケティングの教本』(インプレス)。
_%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.jpg?width=90&name=%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E8%A1%A8%E7%B4%99(%E5%B9%B3%E9%9D%A2)_%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.jpg) |
 |
 |




