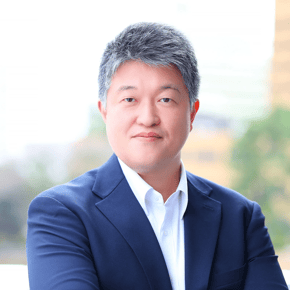かつて、この国が大きく変わった時代が二度あった。
一度目は、幕末から明治維新にかけて。黒船が来航し、植民地化の危機が現実味を帯びるなか、明治の人々は「世界を知る」ことの切迫した必要性に目覚めた。西洋の制度・技術・思想を吸収するため、若き藩士たちは命を懸けて海を渡り、国内では翻訳官や通訳官の育成が急速に進んだ。技術導入や制度模倣は恥ではなく、むしろ国家の生存をかけた知の輸入だった。
二度目は、第二次世界大戦後の廃墟の中である。焦土と化した都市、失われた産業基盤。だが、復興を支えたのは、敗戦のなかにあっても未来を信じ、世界から学ぼうとした技術者たちの執念だった。彼らは、英語の専門教育すら受けていないにもかかわらず、辞書を片手に海外の論文やマニュアルを読み、試行錯誤を重ねながら日本独自の製品開発を進めた。あの高度経済成長の原点には、「情報に飢え、貪欲に学ぶ姿勢」が確かに存在していた。
それから半世紀以上が経った今。インターネットは世界中の情報を即座に手元に届けるが、私たちは果たして、その利便性を「知の力」に変換できているだろうか?
むしろ現在の日本社会は、「静かな情報鎖国」に陥ってはいないだろうか?
多くの企業が、日本語でしかビジネス情報を得ておらず、海外の産業トレンドやベストプラクティスに接することなく、国内市場だけを相手に四苦八苦している。英語が壁になっているのではない。情報に対する執着心と渇望が、かつてほど強くないのだ。
この状態を打破しなければ、日本の再興はない。そしてその突破口は、「BtoBメディア」の再設計にあると、私は強く感じている。
第1部:なぜ「BtoBメディア」なのか?
昨今、メディアに関する話題といえば、もっぱらテレビの不祥事やSNSの炎上ばかりだ。中でも最近のフジテレビのスキャンダルは大きな関心を集めているが、国家戦略という視点で見れば、これは“本丸”ではない。
真に焦点を当てるべきは、BtoB(法人向け)の情報流通の脆弱さである。
BtoCのメディアは、エンタメやニュースを通じて大衆の興味を惹くことに長けている。しかし、産業を、経済を、そして雇用を支えているのは、BtoB領域に存在する数百万社の企業活動だ。これらの企業が正確で深い産業情報にアクセスできなければ、新たな成長は生まれない。
では、現状のBtoBメディアはどうか?
多くは業界団体が発行する月刊誌や、特定テーマに偏った専門メディアにとどまり、最新の海外動向や技術トレンドがタイムリーに届く仕組みは乏しい。加えて、紙メディアからネットメディアへの移行にも成功できず、業界紙の多くが次々と休刊・廃刊に追い込まれているのが現実だ。
その結果、若手経営者や中堅社員が、世界の構造変化をリアルタイムで捉え、戦略やビジネスモデルに反映させる機会が著しく少なくなっている。SNSやYouTubeの断片的な情報では、業界全体の動向を俯瞰することも、仮説を立てて議論を深めることも難しい。
かつて業界紙が担っていた“情報の地ならし”や“共通知識の形成”といった役割が失われつつあり、現場と経営の対話も、業界内の横連携も、どんどん難しくなっている。
このような情報断絶を放置したまま、「DX」や「グローバル化」を標榜しても、企業の意思決定や現場の実行は空回りするだけだ。
だからこそ今、産業の土台となる「BtoBメディア」に対して、国家レベルでの再設計が求められている。
第2部:BtoBメディア再設計に向けた具体策
BtoBメディアの弱体化は、日本産業全体の“視野の狭窄”を招きつつある。では、具体的にどのような手を打てばよいのか。
私たちが向き合うべき課題は、単なる「業界紙の延命」ではない。情報インフラの再構築であり、産業知のサプライチェーン再設計に他ならない。ここでは、そのための4つの柱を提案する。
① 海外の業界メディアとの提携・買収
現在、産業別の最新動向や技術トレンドに関して最も質の高い情報を保有しているのは、欧米やアジアの専門メディアや調査会社である。日本国内においても「翻訳記事」として紹介されることはあるが、量・質・スピードのすべてにおいて不十分だ。
したがって、発想を逆転し、海外の業界誌そのものを買収・提携することを国家戦略の一環とすべきである。
買収後は、日本語による編集・再構成機能を強化し、日本企業の現場や経営層にとって「使える知」として届ける体制を築く。
▷ 期待される効果:
- 世界の技術・市場動向を“週次”で国内に展開可能に
- 「翻訳記事」ではなく、「日本市場に最適化された情報」提供が可能に
- 海外発の産業ベストプラクティスへの迅速な気づきと応用
② AI翻訳・要約技術の導入による高速コンテンツ化
現在の生成AIと翻訳AIは、もはや“補助ツール”ではなく、“情報編集者のパートナー”としてのレベルに達しつつある。そこで、日本語メディアが抱えていた人手不足・翻訳負荷・専門知識の不足といった課題を、AIによる一次処理と編集者による監修の組み合わせで突破する。
▷ 実装イメージ:
- 英語・中国語・ドイツ語などの主要業界紙を自動収集・翻訳・要約
- 編集チームが業界別に選別し、「3分で読める」「深掘り分析」などのフォーマットで再構成
- 配信先は企業の役員・部課長レベルに限定したプレミアム配信にも対応
③ メディアを“教育インフラ”として活用する
紙媒体だった時代の業界紙には、「現場と経営の共通言語をつくる」という側面があった。それを現代に再解釈すれば、BtoBメディアは、次世代経営人材を育成する“産業教育プラットフォーム”へと進化できるはずだ。
▷ 実装例:
- 各業界別に「経営視点」「技術視点」「マーケティング視点」の定期連載を配置
- 解説記事+理解度チェック+ケーススタディ形式で、企業研修にも導入可能に
- 若手~幹部候補への“越境学習”を促す社内ライブラリとして機能
④ 産業横断の知的エコシステムを創る
最後に、個別業界のメディアがバラバラに存在するだけでは、“日本産業の統合的な視野”は生まれない。業界間連携や異業種協業、サプライチェーンの再編など、産業間の知の接続が不可欠な時代においては、横串でナレッジをつなぐ“知的エコシステム”が必要だ。
▷ 構想:
- BtoBメディア間の連携(業界横断シンクタンク機能)
- DX、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーなど横断テーマ特集
- 省庁、大学、民間企業が連携した“産業知のプラットフォーム”としての機能発揮
結び
■ 情報は、すべての掛け算要素に影響する
企業の稼ぐ力とは、突き詰めれば次の方程式に集約される:
稼ぐ力 = ビジネスモデル × 経営者の質 × 組織の実行力
このいずれも、情報環境に大きく依存していることを忘れてはならない。
■ ビジネスモデルは、世界の動きから生まれる
革新的なビジネスモデルとは、ほとんどの場合、他業界や他国の成功例の変形だ。
つまり、「世界の今」を知っている企業こそが、新しい仕組みを先に取り込める。
情報に閉ざされ、日本語の島に閉じこもった企業に、それができるだろうか?
■ 経営者の質は、視野と問いの深さで決まる
経営者の思考の幅と深さは、日々接する情報の質と量によって決まる。
意思決定の基準を形成するのは、日々浴びている情報であり、世界の事例であり、産業構造の解像度だ。
つまり、情報は経営判断の“燃料”そのものである。
■ 組織の実行力は、共通言語によって動く
現場が動かない、戦略が浸透しない──その原因の多くは、「共通言語の不在」にある。
もし経営と現場が同じ外部事例を知り、同じ業界構造を理解していれば、施策の理解と共感は圧倒的にスムーズになる。
情報の共有は、組織における実行力の“インフラ”なのだ。
■ 情報は、すべての掛け算の土台にある
いま日本企業に必要なのは、「情報に飢える感覚」を取り戻すこと。
かつて明治の人々が、そして戦後の技術者たちがそうであったように、世界から貪欲に学び、自らの武器に変える力を持つこと。
そして、そのためにBtoBメディアという“産業の血流”を再設計すること。
情報は、経営のすべてを左右する。
だからこそ、情報から日本を再起動させよう。