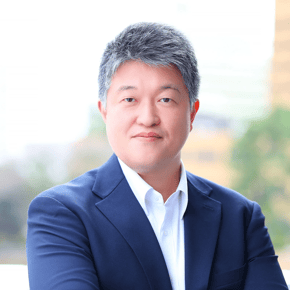この関税政策は、単なる経済制裁ではない。交渉カードとしての意味を持ちつつも、実際に企業の意思決定や国際ビジネスの重心を変え始めている。アメリカに依存してきた企業が今、次の市場を探し始めている。その先に見えてくるのが「日本」だ。
本記事では、この「脱アメリカ」の動きがどのように日本市場に波及してくるのか、そしてそれが日本企業にとって「チャンス」なのか「脅威」なのかを、構造的に整理してみたい。市場の再編というグローバルな流れのなかで、私たち日本企業は何を見極め、どのように行動すべきか——その視点を考えてみたいと思う。
「脱アメリカ」の現場で何が起きているのか
ベトナム北部・ハイフォンにある縫製企業「サオマイ・トレーディング・カンパニー」は、製品の6割以上をアメリカに輸出してきた。しかし、関税政策を受け、同社はこうコメントしている。
「新たな関税によりアメリカの消費者からの需要は確実に減る。アメリカ市場のみに頼らないよう、日本など新たな市場を開拓していくつもりです」
出典:ベトナム縫製会社 相互関税を受け「脱アメリカ」模索|テレ朝news
これは、1社の一過性の動きではない。他にも、ASEANや中南米のメーカーが日本市場への再注目を強めている。これまでアメリカという「最大の需要地」に集中してきた供給構造が、今まさに大きく組み替わろうとしているのだ。
ゲーム理論から見た各国の戦略的行動パターン
このような状況は、ビジネス戦略で使われるゲーム理論(※1)的に見れば、非常に合理的な展開とも言える。
(※1)ゲーム理論…複数のプレイヤーが互いの行動を読み合いながら最適な選択をする、戦略的意思決定の理論。
関税のような「強制的なルール変更」が発生した場合、当該国や企業には以下の3つの選択肢が存在する:
- アメリカに譲歩し、投資・提携などの形で歩み寄る
- 報復的な関税や非関税障壁で応酬する
- アメリカ市場への依存度を下げ、新たな市場にシフトする
この中で、もっともリスクが低く、かつ実現可能性が高いのが「3.市場の分散・脱アメリカ」である。とくにアジアや中南米の新興企業にとって、地理的・文化的に距離が近く、経済規模が大きく、かつ政治的に安定した市場として、日本が強く意識されている。
中国は市場としての規模は大きいものの、自国内の製造力が強く強い中国メーカーが多数存在するので、多くの企業にとって、輸出先としての魅力は相対的に低いだろう。一方で欧州は、物流距離や規制の複雑さ、商習慣の違いなどから、短期的なシフト先としては参入障壁が高い。
その点、日本は品質や信頼を重視する文化を持ち、過去にすでに取引経験のある企業も多く、新たな展開先として現実的な選択肢となる。特にベトナム、タイ、インドネシアなどのASEAN諸国にとっては、「脱アメリカ」を実行する上での最有力候補として日本が浮上しているのだ。
日本企業にとっての「チャンス」と「脅威」
この「脱アメリカ」の動きは、日本企業にとって大きな二面性を持っている。
まず、明確なチャンスとしての側面:
- 海外企業が日本企業にOEMやサプライチェーンの再構築を依頼する可能性
- 輸出先として日本市場が重視され、販売チャネルの拡大が期待される
- 技術提供や共同開発、販路支援などでのパートナー機会が増える
たとえば、東南アジアの電子部品メーカーが日本の大手家電メーカーに直接提案を行ったり、インドのIT企業が日本企業向けの開発拠点を拡張したりといった動きも考えられるだろう。
だが同時に、日本企業にとって「脅威」となる可能性も孕んでいる。
- 価格競争力を持つ企業が日本市場に直接参入してくる
- 既存の取引先が、より安価な海外企業に乗り換えるリスク
- パートナーとして受け入れた企業が、後に競合へと転じる可能性
特に、縫製やアパレル、電子部品、日用品OEMなどの業界では、「競合」としての海外プレイヤーの台頭が現実的な懸念だ。
“競合”か“共創”か、日本企業の選択肢
では、日本企業はこの状況にどう向き合うべきか?
私が重要だと考えるのは、単なる受け身の対応ではなく、「自らの選択によって、脅威をチャンスに変えていけるかどうか」という視点である。そのために必要な観点は、「防衛」と「攻め」の2つに集約される。
1.防衛:競争環境の変化を想定したポジショニングの再設計
まず、自社が置かれている市場や産業において、「どのような競合が、どのような強みをもって参入してくる可能性があるか」を冷静に分析する必要がある。
安さ、スピード、量産体制といった新興国企業の武器に対して、日本企業が本来持っている強み(品質、継続性、提案力、信頼性)をどこまで打ち出せているか。単に「うちは高品質です」と語るだけでなく、その品質がなぜ重要か、どのような結果を生むかまで伝えられているだろうか。
改めて問い直してみてほしい。
- 自社の差別化ポイントは何か? 価格以外で選ばれる理由は何か?
- 顧客が意思決定するプロセスで、自社の価値はどう認識されているか?
- 競合が現れたとき、それでも顧客に選ばれる自信はあるか?
こうした問いを重ねることが、価格競争に巻き込まれない「強さの再定義」につながっていくはずだ。
そしてその“再定義”の先にあるのは、経営としての意思決定。
つまり「戦うフィールドと、戦わないフィールドを決める」こと。全方位戦略をやめて、メリハリをつけるということである。
2.攻め:共創の視点でパートナーを選ぶ意思決定
すべての新興国企業が競合になるわけではない。むしろ、彼らの強みと日本企業の強みが補完関係にある場合、協業によって新たな市場価値を生み出すことができる。
たとえば、海外のスピード感ある生産体制を活かしつつ、日本の設計や品質保証で付加価値を高める。あるいは、国内市場に閉じていた製品や技術を、第三国市場向けに共に再設計する。そうした共創の取り組みは、これからの競争環境において不可欠な選択肢となるだろう。
特に注目すべきは、「市場そのものが再編されている」今だからこそ、従来では出会わなかったパートナーとつながれるチャンスが生まれているという点だ。
共創には、リスクも伴う。文化や商習慣の違い、意思決定のスピード差など、乗り越えるべき壁も多い。しかし、その壁を乗り越える意志と構えがある企業こそが、次の市場で勝ち残るのではないかと私は考えている。
すなわち、いま私たちに求められているのは、自社の立ち位置を守るだけではなく、新たな関係性を築く力である。競争と共創、二つの力を併せ持つことが、これからの企業経営に不可欠な要素となっていくだろう。
まとめ:変化を脅威にしないための「行動」
今回の「トランプ関税」は、一見すれば遠い国の出来事に思えるかもしれない。だが、その波紋は、確実に日本市場にも押し寄せている。
「変化」とは、それ自体がチャンスでも脅威でもない。それにどう備え、どう動くかで、意味が変わってくる。
現状維持ではなく、あえて市場を見直す。あえて外のパートナーと向き合う。あえてポジショニングを言語化し直す。
その行動こそが、次の未来を拓く鍵になるのではないかと思う。
■CEOブログシリーズ
CEOブログ第1回|眠れる巨人、日本企業よ! グローバル競争激化の中、 営業の非効率性があなたの未来を蝕む!
CEOブログ第2回|営業不足で会社が潰れる時代――今すぐ変わるための営業組織改革
CEOブログ第3回【前編】|アメリカ企業はなぜ日本企業の50倍のマーケティング予算を使うのか?
CEOブログ第3回【後編】|アメリカ企業はなぜ日本企業の50倍のマーケティング予算を使うのか?