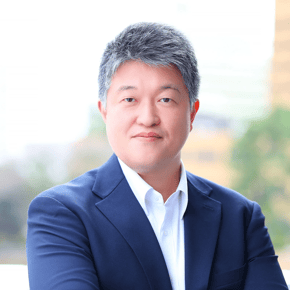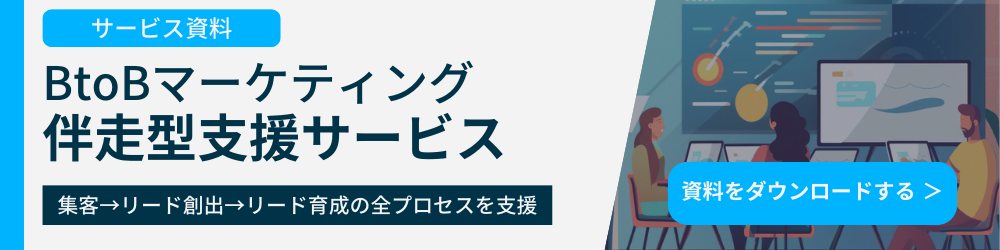今、BtoB企業のマーケティングにおいてオウンドメディアの重要性が高まっています。
かつては広告を出せば認知が広がり、リード獲得につながりました。しかし、近年は広告での獲得コストの高騰や情報の飽和により、広告施策だけでは思うような成果が出にくくなっています。さらに、見込み顧客の購買行動も変化し、「自ら調べた情報」を重視する傾向が強まっているのです。
こうした中、見込み顧客に適切なタイミングで価値ある情報を提供し、信頼を獲得することがこれまで以上に重要になっています。そのためには、オウンドメディアの活用が効果的です。
本記事では、まずオウンドメディアの基礎を解説し、そして成果を最大化するための戦略をプロの視点から深掘りします。
「オウンドメディア運営で本当に成果を出すには?」
その答えを一緒に探っていきましょう。
目次
TABLE OF CONTENTS
オウンドメディアの定義と役割
オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自社で所有・運営するメディアを指します。具体的には、企業のブログ、コーポレートサイト、コンテンツマーケティングのための専門サイトなどが該当し、企業が独自に情報を発信して顧客との接点を持つための重要な手段です。
オウンドメディアは、マーケティング施策においてペイドメディア(Paid Media)や アーンドメディア(Earned Media)と組み合わせて活用されることが一般的です。これら3つのメディアは「トリプルメディア」と呼ばれ、各メディアの特徴を理解し、適切に使い分けることで、より効果的なマーケティング戦略を構築できます。
|
項目 |
オウンドメディア (Owned Media) |
ペイドメディア (Paid Media) |
アーンドメディア (Earned Media) |
|
特徴 |
企業が所有・運営するメディア |
費用を支払って露出を獲得するメディア |
口コミやSNSでの拡散、メディア掲載など、第三者が自主的に発信するメディア |
|
具体例 |
企業ブログ、コーポレートサイト |
Google広告、SNS広告(Facebook Ads、LinkedIn Ads)、YouTube広告、などの広告媒体 |
SNS、口コミサイト、レビューサイトなど |
|
メリット |
長期的な情報資産となる。SEOで自然流入を増やせる。ソートリーダーシップの強化に貢献。 |
即効性があり、短期間で集客できる。ターゲットを細かく絞れる。 |
信頼性が高く、コストをかけずに認知拡大できる。拡散力が強い。 |
|
デメリット |
効果が出るまでに時間がかかる。運用の手間がかかる。 |
広告費を払い続けないと流入が止まる。ユーザーに敬遠されることも。 |
コントロールが難しく、ネガティブな情報が拡散するリスクもある。 |
オウンドメディアは「企業が自由に運用できる、自社で管理可能なメディア」という点で、ペイドメディアやアーンドメディアとは大きく異なります。
即効性のあるペイドメディア、口コミ拡散力のあるアーンドメディアと組み合わせることで、オウンドメディアの価値を最大限に引き出すことができます。
短期施策と長期施策をバランスよく組み合わせ、持続的にリード獲得・ブランド構築を行うことが重要です。
オウンドメディアとSNS、外部プラットフォームの違いは?
自社で情報発信をする際、企業は SNS(X、Facebook、LinkedInなど) や外部プラットフォーム(noteなど)との使い分けを検討する必要があります。これらのメディアも情報発信の場として活用されますが、オウンドメディアとは異なる特性を持っています。
|
項目 |
オウンドメディア |
SNS |
外部プラットフォーム |
|
特徴 |
企業が所有・運営するメディア。独自ドメインで運用し、長期的に情報を蓄積できる。 |
ユーザーとのコミュニケーションや拡散を目的とする短文・即時性の高い投稿。 |
外部サービス上で記事を投稿できるプラットフォーム。手軽に始められるが、運営元のルールに依存する。 |
|
具体例 |
企業ブログ、コーポレートサイト |
X(旧Twitter), Facebook, LinkedInなど |
noteなど |
|
メリット |
自然流入を継続的に獲得できる。ブランド資産として蓄積可能。 |
リアルタイム性が高く、拡散力がある。フォロワーとの直接交流が可能。 |
初期コストがかからず、手軽に記事を投稿できる。既存ユーザーの流入が見込める。 |
|
デメリット |
効果が出るまでに時間がかかる。継続的なコンテンツ制作が必要。 |
投稿が流れてしまい、長期的な情報資産としては活用しにくい。 |
プラットフォームの規約変更やサービス終了のリスクがある。SEO評価も外部ドメインに依存するため、自社サイトの検索流入には貢献しにくい。 |
|
活用方法 |
自社サイトの資産としてコンテンツを蓄積し、リード獲得やブランディングを強化する。 |
記事の拡散・認知向上のために活用し、自社サイトへの流入を促す。 |
カジュアルなコンテンツや、既存コミュニティ向けの発信に適している。 |
SNSや外部プラットフォームは、「スピーディーな情報発信・拡散」に優れている一方、情報の資産化が難しいという特徴があります。
一方で、オウンドメディアは「長期的な検索流入の獲得・顧客との関係構築・ブランド強化」 に優れ、SNSや外部プラットフォームと組み合わせて運用することで、短期・中長期の両面で成果を最大化できます。
特に、SNSはオウンドメディアへの流入を増やすための導線として活用し、「情報の蓄積はオウンドメディア、拡散はSNS」という戦略的な使い分け が理想的です。
オウンドメディアの強みとは?
これまで見てきたオウンドメディアの強みを、次の4つの視点で整理してみましょう。
- 検索エンジンからの流入を継続的に獲得できる
SEOを適切に施せば、Google検索経由で新たな見込み顧客を継続的に呼び込むことができる。SNSの拡散とは異なり、一時的ではなく「安定的に流入を生み出せる」点が大きな違い。 - 顧客との関係構築ができる
有益な情報を提供し続けることで、見込み顧客との接点を増やし、購買意欲を高められる。SNSでは「一過性の関係」になりがちだが、オウンドメディアなら「企業の持つ価値を体系的に伝え、信頼を構築できる」。 - 企業のブランド価値を高める
自社の専門性や独自の知見を発信することで、業界内でのポジションを確立できる。外部プラットフォームに依存せず、企業が主導権を持ってブランディングを進められる点が強み。 - 長期的な資産として活用できる
一度作成したコンテンツがWeb上に残り続け、広告を打たなくても検索流入を獲得できる。SNSの投稿は時間とともに埋もれてしまうが、オウンドメディアのコンテンツは「価値のある情報」として継続的に機能する。
オウンドメディアを戦略的に運営することで、単なる情報発信の場ではなく、持続的に集客できる仕組みや企業のブランド価値を高めるマーケティング基盤を構築することが可能になります。広告やSNSの投稿が短期的な施策であるのに対し、オウンドメディアは 企業の資産として機能し、時間の経過とともに競争優位性を高められる点が大きな強みです。この特性を活かし、適切な戦略を立てた上で運営を行うことが、マーケティング成果を最大化する鍵となるでしょう。
オウンドメディアを立ち上げるには?
では、オウンドメディアを立ち上げるには何から始めればよいのでしょうか?
まずは「目的の明確化」「適切な運営体制の構築」「コンテンツ設計」「KPI設計」「継続的な運用」の5つのステップを押さえることが重要です。
1. 目的の明確化:何のために運営するのか?
オウンドメディアの成功は、「どんな成果を求めるのか?」を明確にすることから始まります。目的によって、必要なコンテンツや運営方針が大きく変わるため、ここを曖昧にしたまま運営を始めると、後々方向性がブレる原因になります。
代表的な目的と、それに応じた施策の考え方は以下の通りです。
- 自然流入を増やしたい場合
自然流入を増やすために、ターゲットが興味関心を持っているテーマを調査し、課題解決につながる記事を継続的に作成する必要があります。 - リードを獲得したい場合
ただ情報提供をするだけではなく、読者をホワイトペーパーのダウンロードやウェビナーへの誘導つなげる仕組みが必要です。CTA(コールトゥアクション=ユーザーに具体的な行動を促すための要素。資料ダウンロードやお問い合わせのリンクなど)を適切に配置し、フォームの入力ハードルを下げることがポイントになります。 - ブランディングを強化したい場合
競合との差別化や、自社の強みを訴求できる独自の視点を打ち出し、専門性や企業の価値観が伝わるコンテンツを発信することが重要です。例えば、経営層のインタビューや独自の業界分析記事などが効果的です。
目的を明確にした上で、「誰に、どんな情報を届けるのか?」という軸を持つことで、ぶれない運営が可能になります。
2. 適切な運営体制の構築
オウンドメディアは、単発で記事を公開するだけでは成果が出ません。継続的に運営するための体制を整えることが成功の鍵です。
- 社内で運営する場合
マーケティングの知見があり、読者目線でコンテンツ制作・編集・分析のスキルを持つ人材を確保する必要があります。特に、自社の業界トレンドや顧客目線に明るい人材がいるかどうかは、オウンドメディアの成否を分けるポイントとなります。 - 外部委託する場合
全てを外部に依頼するのではなく、戦略設計やコンテンツの方向性は社内で決め、制作部分を外注するのが理想的です。単にコンテンツを制作できるというだけではなく、SEOやコンテンツマーケティングに強い制作会社を選定することが重要になります。
オウンドメディアの運営には、記事作成だけでなく、企画・編集・分析・改善といった幅広い業務が発生するため、それを担う体制を整えておくことが不可欠です。
3. コンテンツ設計:ターゲットとテーマの明確化
オウンドメディアで成果を出すためには、「誰に向けて、どのような情報をどのように提供するのか?」を明確にしましょう。
- ペルソナの設定
どのような課題を持つ人がターゲットなのかを具体的に定義します。BtoBの場合は、業種・職種・意思決定プロセスなどを考慮することがポイントです。
▶関連記事:BtoBマーケティングのペルソナ戦略完全ガイド|効果的な作成と活用の実践手順
- コンテンツの軸を決める
企業の強みを活かしつつ、ターゲットの興味関心に合ったテーマを選定します。例えば、「マーケティング担当者向けの最新トレンド」「製造業のDX推進に関する情報」など、一貫性のあるテーマ設定が重要です。 - コンテンツフォーマットの決定
ブログ記事だけでなく、動画やホワイトペーパー、インフォグラフィック(図版)など、ユーザーが情報を受け取りやすい形で発信することも重要です。例えば、ノウハウ記事を作成した後に、その内容をスライド資料にまとめることで、活用の幅が広がります。
▶関連記事:【2025年最新】コンテンツ制作の基礎知識を網羅!プロに聞く成功のポイントとは?
4. KPI設計:成果を可視化する指標とは?
オウンドメディアの効果を測るために、適切なKPIを設定することが重要 です。目的ごとに、以下のような指標を設定するとよいでしょう。
- 検索流入を増やしたい場合
「検索エンジン経由の流入数」「検索順位の推移」など - リードを獲得したい場合
「ホワイトペーパーのダウンロード数」「ウェビナー申し込み件数」など - ブランディングを強化したい場合
「ブランドワードでの検索上位表示」「再訪率」など
数値目標を設定し、定期的に分析・改善を行うことが、成果につなげるポイントです。
5. 継続的な運用
オウンドメディアの運営は、継続することが最も重要な成功要因です。しかし、多くの企業が「ネタ切れ」「リソース不足」「KPIの未達」などの理由で、途中で更新が止まってしまいます。これを防ぐためには、以下の3つのポイントを押さえておくとよいでしょう。
- コンテンツカレンダーを作成し、計画的に運営する
「どのテーマの記事を、いつ公開するのか?」を事前に決めておくことで、運営の継続性が高まります。 - 社内外のリソースを適切に活用する
すべてを社内で対応するのではなく、外部パートナーの活用や、既存のコンテンツの再利用(リライトや動画化)も検討すると、負担を分散できます。 - 定期的にKPIを見直し、改善を続ける
毎月のレポートを作成し、成果が出ているか否かを分析し、改善を繰り返すことが重要です。たとえば、CVR(コンバージョン率)が低い場合はサイト内導線を改善する、直帰率が高い記事はCTAの位置を見直すなどの施策を講じることで、効果を高めることができます。
このように、オウンドメディアは継続的な運用によって初めて成果が生まれるもの です。単発の施策ではなく、計画的なコンテンツ発信と定期的な改善を続けることで、長期的な検索流入やリード獲得の基盤を築くことができます。継続的な運営体制を整え、オウンドメディアを企業の成長を支える資産へと育てていきましょう。
第一人者に聞く!成果を出すオウンドメディア運営とは
ここまで、オウンドメディアの基礎知識から実践的なノウハウまでをご紹介してきました。では、実際にオウンドメディアを成功に導くには、具体的にどのような点に気をつければよいのでしょうか?
今回は、オウンドメディア運営の第一人者・弊社イノーバ代表の宗像にインタビューを実施しました。2011年にイノーバを創業して以来、当時アメリカで主流だったコンテンツマーケティングをいち早く日本に紹介し、数々のBtoB企業のオウンドメディア運営に携わってきた宗像。豊富な経験をもとに、オウンドメディア運営で押さえておきたいポイントをたっぷり語ってもらいました。
▶代表・宗像の詳しいプロフィールを読む
質問1:オウンドメディアを運用した方が良いケースと、運用しない方が良いケースはありますか?
宗像:
オウンドメディアの目的・狙いをはっきりさせるのが大事です。
まず、運用しない方がいいケースからいきましょう。
①客単価が安い。コンビニ、スーパー、ドラッグストアなどで売っているようなものはあまりオウンドメディアとは相性がよくないと思います。
結局は、認知度と小売りの棚のシェアですから。
②SEOノウハウ、記事制作ノウハウ、導線改善ノウハウ等が必要なので、こういったノウハウが、外注パートナー含め、社内外で確保できない場合は、取り組まない方がいいでしょう。
③オウンドメディアが一般化しており、すでに競合のオウンドメディアが乱立してしまっている場合も、後発で勝つため戦略を立ててからの方がいいでしょう。
逆に、運用した方がいい場合は、
①客単価が高い、商談サイクルが長い、商材がわかりにくい、などの場合、やる方がいいケースが多いです。顧客教育、リード育成が必要になるからです。
ただし、オウンドメディアだからといって、独立したメディアにしないといけない訳ではないです。ブログ、コラム型でも十分です。
②顧客が、オンラインで情報収集をよくする商材の場合は、オウンドメディアで接点確保、リード獲得の重要性が高いです。
③広告依存で獲得コストが高く困っているなどの場合は、オウンドメディアの取り組む事で、獲得コストを下げられる可能性があります。(デジタルマーケティングで成果を出している会社のウェブサイトは、検索流入比率が半分以上、場合によっては8割超を占めているケースが多いです。
質問2:オウンドメディア運営を「内製 vs 外注」どちらにすべきでしょうか?
宗像:
結論、併用すべきだと思います。
検索エンジンの変化は、本当に早くて、正直、本来プロであるはずの、SEO会社でも時代遅れの知識でやっているところが沢山あります。ましてや、社内の人材で、検索エンジンの変化に追随して、SEO対策の施策を適切に維持するのは現実的ではないからです。
ただし、外注だけだと、コンテンツの質が低い会社も多く、十分な品質が出ないケースが多くあります。「SEOコンテンツは、質よりは量なのです」という、時代遅れの手法を進める会社も沢山あります。
外部パートナーも使いつつ、コンテンツの品質面は、社内の人がしっかりとチェックするのが重要だと思います。(社内でほぼ書き直しているような例は、外注の意味がないので、外注先を見直すべきとは思います)
質問3:少ないリソースでもオウンドメディアを継続する方法は何でしょうか?
宗像:
オウンドメディアは継続的に運営すべきものなので、社内、社外問わず、ある程度のリソースは覚悟しないとダメです。
リソースを抑えるための工夫としては、「専門家」にインタビューする、ウェビナーやホワイトペーパー等の既にあるコンテンツを使いまわす(コンテンツ・リパーパスと言います)などがあり得ます。
質問4:オウンドメディアで「ビジネス成果」を出すにはどうすればよいのでしょうか?
宗像:
成果が出ていない要因の分析をするのが大事です。
原因は様々です。
①検索流入が少ない。狙ったキーワードで上位表示できていない。
②検索流入はあるが、本来狙うべきではない、ターゲット外のユーザーが流入している。
③検索流入はあるが、直帰してしまっており、問い合わせやリード獲得につながっていない。
①、②は、再度、SEO戦略、キーワード戦略を見直す必要があります。
③は、記事のリライトや導線改善、リード獲得の工夫(CTAといいます)などの追加が必要となります。
オウンドメディアを、コーポレートサイト、サービスサイトと別に独立運用してしまっていると、せっかく流入したユーザーが、自社の商品・サービスや事例に気付くことなく、離脱してしまうことが起きます。(コンバージョンポイントが無い状態です)これも要チェックです。
質問5:「リード獲得につながる記事」と「読まれるだけの記事」の違いは何でしょうか?
宗像:
今は、ユーザーの検索行動が洗練されてきて、必要な情報だけ取って、離脱するユーザーが増えています。
最近は、ダウンロード資料を設置する企業も増えており、CTAも、内容が刺さらないと、バナーがクリックされない、ダウンロードされないというケースが増えています。(これらは、バナーブランドネスと呼ばれます)
記事そのものに、「読みごたえ」とか、「気づき」を入れる事で、続きを読みたい、関連の資料をダウンロードしたいという心理状態、態度変容を生み出すのが重要かと思います。
▶関連記事:【2025年最新】コンテンツ制作の基礎知識を網羅!プロに聞く成功のポイントとは?
質問6:SEOを意識した運営をしているのに、流入が増えないのはなぜでしょうか?
宗像:
ここ2~3年は、生成AIが出てきた事で、検索エンジン対策、SEOの手法、抑えどころも、相当変わってきています。
特に注意すべきは、
①サイト品質が相当問われるようになっている
②従来はプラス評価だった、コンテンツの量が逆にネガティブ評価を受ける事が増えている
③ここの記事の独自性、ユニーク性が問われる(EEAT=Googleがコンテンツの品質を評価する際に重視する4つの要素。Experience / 経験、Expertise / 専門性、Authoritativeness / 権威性、Trustworthiness / 信頼性)などです。
SEO対策の知識や手法のアップデート、検索エンジンから適切な評価が取れるようなサイトになっているのか、などを見直す必要があるのかなと思っています。
▶関連記事:検索エンジンは生成AIコンテンツをどう見ている?SEO上の影響は?
質問7:オウンドメディアのKPIはどう設定すべきですか?
宗像:
KPIは、BtoBであれば、問い合わせ、リード獲得、それにつながる、質の良い流入をセットするのがいいかなと。逆に、流入数だけをおうと、質が下がるので要注意です。
BtoCであれば、オウンドメディアから売上にどれだけつながっているのか、ECサイトへの遷移数とかを追います。
質問8:生成AI時代において、オウンドメディアの戦略はどう変わると思いますか?
宗像:
ここはもう激変すると思います。
SEO対策の部分が大きく変わっているのは、前述の通りです。
ただ、それ以上にインパクトがあると思うのは、質の低いコンテンツが乱造されて、自社のコンテンツ、自社のオウンドメディアが埋もれるリスクが非常に大きくなるということです。
質の良さを訴求するために何ができるのか、自社のオリジナルの情報を出すためには何ができるのかを考える必要があると思います。
BtoB文脈であれば、アルゴリズム依存しないということで、直接届けられるチャネルとして、メルマガ、メールをしっかりと活用する必要があると思います。
▶関連シリーズ記事:生成AI × BtoBマーケ①|「課題訴求型」コンテンツの必要性
まとめ:オウンドメディア運営を成功させるために
オウンドメディアは、単なる情報発信の場ではなく、長期的な集客基盤とブランド構築を支える重要な資産です。
成功のポイントは、目的を明確にし、適切な戦略をもとに継続的に運用すること。検索流入の増加やリード獲得、ブランド強化といった目的に応じたコンテンツ設計を行い、KPIを設定して定期的に成果を分析し、改善を繰り返すことが不可欠です。
特に生成AI時代においては、独自の視点や専門性を活かした質の高いコンテンツを提供することが、他社との差別化において重要です。戦略的な運営を続けることで、オウンドメディアは企業の持続的な成長を支える重要な資産となるでしょう。