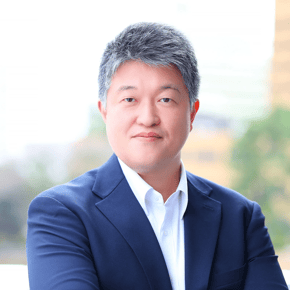こんにちは、イノーバの宗像です。
今回は社内で実施した読書会『マンガでやさしくわかる知識創造』第1章の振り返りと、そこから得られた気づき、そして私自身の10年越しの“知識創造”との向き合い方について書いてみます。
SECIモデルとの出会いは、富士通時代の同期との会話から
「“知識は創造されるもの”って、面白いと思わない?」
富士通時代の同期、羽山和宏さん(現:富士通株式会社 経済安全保障室 エグゼクティブディレクター)からそう言われたのは、もう10年以上前のことです。彼は当時、一橋大学のMBAで野中郁次郎先生の授業を受けており、「SECIモデル」という知識創造の理論を学んでいました。
彼の言葉に興味を持ち、野中先生の代表作『知識創造企業』を買って読んでみたものの…正直、当時の私には難しくてピンときませんでした。
イノーバ創業と“知識”の重みの再認識
それから数年が経ち、私はイノーバを創業。マーケティング支援の現場でさまざまな課題と向き合う中で、ふとした瞬間に気づくのです。
「これって、あのときの“SECIモデル”の話なんじゃないか?」
暗黙知を共有する場があるチームは成果が出る。
成功の理由を言語化し、横展開できる組織は強い。
属人化に陥った業務はボトルネックになる。
これらの現象が、SECIモデル(共同化→表出化→連結化→内面化)で説明できると腑に落ちた瞬間でした。
西原(廣瀬)先生との出会いと「SECILALA」
再び羽山さんに連絡を取ったところ、『マンガでやさしくわかる知識創造』の著者である、西原(廣瀬)先生(※)をご紹介いただくことに。
(※)現在はお名前を「廣瀬」に変更されているため、以後「廣瀬先生」と表記させていただきます。
廣瀬先生は、NECで海外事業に従事された後、一橋大学大学院で野中先生に師事。現在は立教大学経営学部の准教授/学部長として、野中先生のご遺志を継がれ、知識創造理論を研究・教育されています。
廣瀬先生にご紹介させていただき、「SECILALA(セキララ)」というナレッジマネジメントの実践者の会にも出会う事が出来ましたし、主催者の村上修司さんにも出会うことが出来ました。SECILALAでは、知識創造に取り組むビジネスパーソンが、企業の垣根を越えて気兼ねなく交流する事ができる場が広がっており、素敵な場だなと思いました。
参考:村上修司さんのnoteをご紹介。村上さんは、『マンガでやさしくわかる知識創造』のモデルになっているそうです!ちなみに、主人公たちの名前も村上さんのお名前に由来しているとのこと(廣瀬先生談)。
読書会から生まれたイノーバ社内の“気づき”
今回の読書会では、SECIモデルに初めて触れたメンバーも多く、特に「暗黙知と形式知の違い」が印象に残ったようです。
|
種類 |
内容 |
例 |
|
形式知 |
言葉や数値で表せる知識 |
マニュアル、手順書、報告書など |
|
暗黙知 |
感覚・経験・思考のクセ |
提案の“間”、直観、ベテランの所作など |
「普段、自分がなんとなくやっていることに、実は意味がある」
「それを言語化するのは難しいけれど、伝わったときにチームが強くなる」
という声が、多くのメンバーからあがりました。
イノーバにおけるSECI的な動き
読書会を通じて再確認できたのは、イノーバの中でもすでに“知識創造的な営み”は始まっているということです。
たとえば:
- 日報:日々の「気づき」や「もやもや」が詰まった、知の原石の集積所。読み返すだけでアイデアが生まれる。
- Zoom会議の文字起こし:何気ない議論にこそ、“暗黙知”のヒントが宿る。それを文字で拾えるのは大きい。
- Slackやチャットワーク、Notion:気づきの断片を気軽に共有し、自然と知識が可視化されていく場になっている。
これらの動きは、まだ部分的かもしれませんが、まさにSECIの回転が始まっている証拠だと感じます。
心理的安全性が、「知識共有」の前提になる
「ナレッジを出したいけど、評価されそうで怖い」
「間違っていたらどうしよう…」
こうした感情は誰にでもあるものです。
だからこそ、「どんな発言も歓迎される」「ツッコミなしで受け止める」場づくりはとても大切。
読書会でも、“心理的安全性”と“知の場”の設計について、多くの意見が交わされました。
明日からできる、小さなアクション
読書会で出たアイデアの中から、すぐに始められそうなものをいくつか紹介します。
- 「なんとなくやっていること」を日報にメモしてみる
- 会議の中で「今のって、暗黙知じゃない?」とツッコミ役になる
- 他人のやり方に“なぜ?”を投げてみる
- Slackに「気づきチャネル」をつくってみる
こうした積み重ねが、知識の共有→連携→内面化というサイクルを自然と生み出していきます。
最後に:知識とは“人を動かす力”である
読書会の中で、あるメンバーがこう言いました。
「知識創造って、資料をつくることじゃなくて、“人を動かすこと”だと思う」
それは私がイノーバを立ち上げてから、ずっと感じてきたことでもあります。
本や会議資料だけではなく、誰かの経験、失敗、直感、言葉にできない工夫こそが、人と組織を動かすエネルギーになる。
これからも、私たちが「知を共有する文化」を少しずつ育てていけたらと思います。
次回予告
次回の読書会では第2章を読み進めながら、
「知識を生む組織づくり」「仕組みと場のデザイン」についてディスカッション予定です。