みなさんは「ウェビナー」をご存知でしょうか。これまで日本ではあまり注目されていませんでしたが、マーケティングの本場であるアメリカでは、低コストながら確実に顧客にアプローチできるマーケティング施策として、多くの企業が取り組んでいます。
この記事では、ウェビナーが近年特に注目を集める理由や活用メリット、実際に開催する際の注意点など、これから始める方が知っておくべき情報をまとめました。
そもそも、ウェビナーとはどんなツール?
ウェビナーとは「ウェブ(Web)」と「セミナー(Seminar)」を組み合わせた造語で、名前の通りインターネット上で開催されるセミナーを指します。Webセミナー、またはオンラインセミナーと呼ばれることもあります。
もともとウェビナーはアメリカで生まれたマーケティング施策です。アメリカは国土が広く、また企業の拠点も一極集中ではないという事情があり、1社訪問するだけでも移動費や時間がかさむことがビジネス上の課題とされていました。そのため販売代理店を設置したり、営業代行サービスを活用したりとさまざまな対策が取られていましたが、運営コストがかかることや本社からのメッセージがうまく届かないなどの問題がありました。
こうした背景の中、オンラインのコミュニケーションツールの発展とともに一般化したのがウェビナーです。オンラインで行われる講演会や講義、研修などの参加者は、そのまま自社の製品やサービスに興味のある潜在顧客であるケースが多く、効率的により多くの人にアプローチできる方法として、重要なマーケティング施策の一つとなっていったのです。
日本はアメリカほど国土が広くなく、地方の顧客でも新幹線や飛行機で日帰り訪問できるため、これまであまりウェビナーは普及していませんでした。また対面でのコミュニケーションを好む文化があることも、ウェビナーがそれほど注目されなかった一因といえるでしょう。
しかし、最近ではWebマーケティングの普及により、少ないリソースで多くの顧客にリーチできる手法が一般化しています。そのため、営業活動においても合理化が求められ、オンラインで顧客にアプローチする手法が注目を集め始めています。さらに、昨今の新型コロナウイルスの影響で、オフラインイベントやセミナーの開催が難しくなっていることも手伝い、ウェビナーが急激に広まっているのです。
ウェビナーが注目されている理由と、ウェビナーを開催するメリット
前述したように、これまで日本ではイベントやセミナーの開催はオフラインが主流でした。そのため、オンラインで開催するウェビナーで本当に成果が期待できるのか、懐疑的に感じる人もいるかもしれません。
ウェビナーの開催は、具体的に以下のようなメリットがあります。
配信者側のメリット
地理的な制約がない
大阪や名古屋、福岡などの他都市はもちろん、これまでセミナーやイベントがあまり開催されていなかった地方の顧客にもアプローチが可能。また、国外の見込み客にリーチできるのも製品やサービスによってはメリットといえます。
開催コストがおさえられる
会場やスタッフの手配が必要なセミナー、イベントに比べると、人件費や会場費がおさえられるため低コストで開催することができます。
参加者側のメリット
地理的な制約なく参加できる
ウェビナーはすべてオンラインで開催されるため、地方や海外などに住む人でも移動の必要がなく、地理的な制約を受けずに参加できます。
参加のハードルが低い
ウェビナーには匿名で質問する機能やチャット機能もあり、一般のイベントやセミナーに比べて参加のハードルが低い傾向にあります。また、会話がチャットで残ったり、資料を共有する機能が充実しているため、参加後の自習にも適しています。
あとから録画を確認できる
開催側が録画を公開している場合、もし参加できなかった、理解しきれなかった場合でもあとから録画を振り返り、学習に使えるというメリットもあります。
*
このように、ウェビナーは配信者側、参加者側の双方にメリットがあり、それだけ多くの参加者を集めることができる手法です。これはあくまで一例ですが、弊社イノーバでは参加者数が対面セミナーの10倍以上に、また商談につながったケースも2倍ほどにアップしており、ウェビナーでも、オフラインイベントと同じ、もしくはそれ以上の効果を上げられると感じています。
また、ウェビナーは開催後に動画を顧客に提供したり、ダウンロードコンテンツにしたりするなど、セミナーそのものをコンテンツ化しやすいのも大きなメリットです。動画だけでなく、動画の一部を書き起こしてブログやホワイトペーパーにする、セミナー後のQ&Aをコンテンツ化するなどの展開も容易なため、デジタルマーケティング時代には欠かせない施策と言えるかもしれません。
ウェビナーを開催する時のポイント
ウェビナーはオンラインならではの手軽さと集客力が魅力の、新しいマーケティング施策と言えるでしょう。ただ、実際に参加者と対面するわけではないため、従来のセミナーやイベントとは少し異なる点があることに注意が必要です。覚えておきたいポイントを、開催までのステップごとにまとめました。
企画のポイント
この記事ではウェビナーをマーケティング施策の一つとして紹介していますが、参加者は知識やスキルを身につける学びの場として参加していることを忘れてはいけません。時にはノウハウの共有よりも、自社製品やサービスの売り込みに時間を割いているウェビナーも見かけますが、顧客離れの原因となるため長期的な視点で見れば悪手といえるでしょう。参加者の興味のあるトレンドや、自社が解決できる課題感に合致した話題など、顧客ニーズに合致した情報発信が大事です。
【ポイント】
- 難しい内容の場合は、事例やケーススタディを盛り込んでわかりやすい構成に
- オンラインは集中力が早く切れやすいので、30分~1時間程度に収めるのが良い
ツール選びのポイント
ウェビナーを開催するためのツールはさまざまなベンダーから提供されていますが、最初はユーザーも多く機能もしっかりしている「Zoomウェビナー」をおすすめします(弊社イノーバもこれを使用しています)。他のツールを選ぶ場合は、以下のような機能があるかどうかを基準にするといいでしょう。いずれのツールを使う場合でも、事前の動作チェックや音声チェックは必須です。
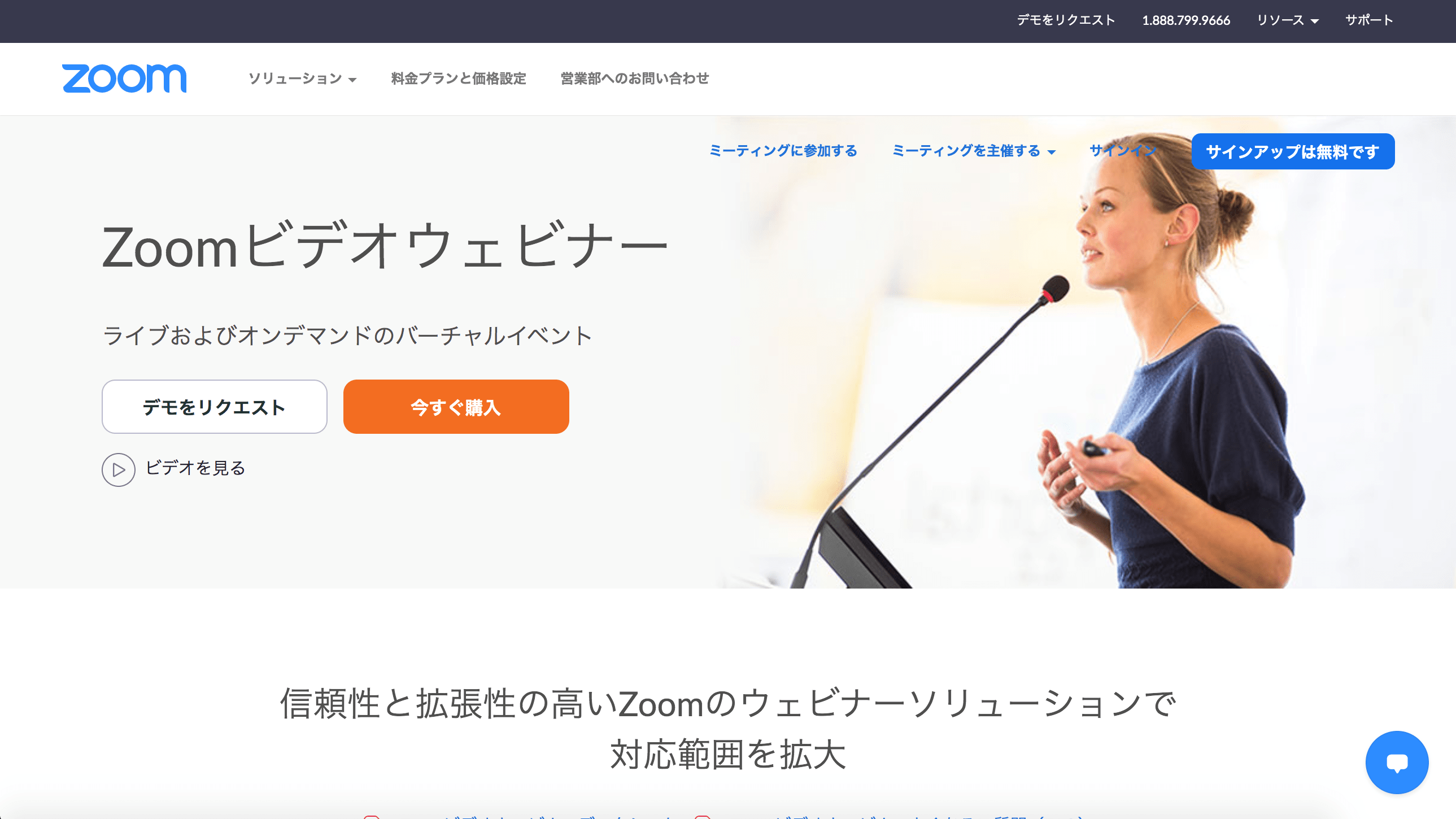
【Zoomウェビナー機能:Zoom公式ホームページより】
【ポイント】
- 画質や音声が安定しているかどうか
- Q&A、チャット、ブレイクアウトセッション、参加者レポートなど、ウェビナーに特化した機能が充実しているか
- ウェビナーを録画することができるか
集客・参加者管理のポイント
ウェビナーの集客にはさまざまな方法が考えられますが、ユーザーにとっては学びの場であることを考えると、まずはすでにコンタクトを取ったことがあり、ある程度の信頼を築けている層へアプローチすることをおすすめします。
【ポイント】
- まずはハウスリストにある顧客へ、メルマガやFacebook広告などでアプローチ
- 申込者には、参加方法の案内・リマインドをメールで数回送る
関連記事|メルマガはBtoBにも効果あり!知っておきたい活用の意義と効果的な送り方
当日運営のポイント
オンラインで開催するセミナーとはいえ、当日ドタバタしてしまったり、事前の準備不足が参加者に見えてしまったりするのは避けたいもの。ウェビナー自体の信用を損なったり、顧客離れの原因になりかねません。事前にしっかりと段取りを確認し、スムーズに運営できるようにしましょう。
【ポイント】
- 当日は必ず機材のチェックをする(特に音声チェックは重要!)
- セミナー中は接続の問題や参加者のトラブルに対応するため、登壇者以外に最低1人は担当を用意する
- 登壇者がセミナーに慣れていない場合や、はじめてウェビナーを開催する場合は必ずリハーサルを行う
フォローアップのポイント
ウェビナーを集客や売り上げにつなげるためには、開催するだけでなく参加者へのフォローアップが欠かせません。セミナー中に商品のオファーを示す、他のウェビナーやサイトに誘導するなど、参加者が次にとって欲しいアクションを明確に示せるようにしましょう。
【ポイント】
- アンケートをとって参加者の課題感を把握する
- 確度の高そうなリードにはできれば当日のうちに、メールや電話でフォローアップする
ウェビナーは今やマーケティング施策の必須手段に
オンラインにより手軽に、低コストで開催できるうえ、見込み客にもアプローチしやすいウェビナー。Webマーケティングとの相性もよく、今後は企業にとってなくてはならない施策となるかもしれません。ライバル企業の一歩先を行くためにも、ウェビナーの開催を検討してみてはいかがでしょうか。
関連動画(イノーバYoutube)|今こそ取り組みたい!ウェビナーの重要性と運用の仕方
関連動画(イノーバYoutube)|ウェビナ―は「飽和」しないのか?他社と差をつけるウェビナー企画のコツ:ご質問回答コーナー



