企業のマーケティング担当者が必ず一度は目にする4P分析。今回は4P分析に至るプロセスと基礎、実際の事例をベースにしたケーススタディを通して4P分析を実践するコツをつかみましょう。
4P分析の前ステップ
4Pとは、マーケティング戦略の立案・実行プロセスの1つである、マーケティング・ミックスに関連する要素であり、
- Product(プロダクト:製品)
- Price(プライス:価格)
- Place(プレイス:流通)
- Promotion(プロモーション:販売促進)
の頭文字をとってまとめられるものです。
マーケティング戦略の立案・実行のプロセスは、以下の6ステップとされます。
- マーケティング環境分析と市場機会の発見
- セグメンテーション(市場細分化)
- ターゲティング(市場の絞り込み)
- ポジショニング
- マーケティング・ミックス(4P)
- マーケティング戦略の実行と評価
まず市場(環境)における自社の強み弱みを把握し、次に自社の立ち位置を決定します。1についてはSWOT分析や3C分析などを、2~4にはSTP分析などが利用されます。そのうえで、「どのような製品をどのくらいの価格でどういう経路で市場に送り出すのか」、「どのようにターゲット層に情報を届けるのか」という戦略を詳細に検討します。その際に利用されるフレームワークがマーケティング・ミックスであり、「4P」なのです。
関連記事:
4P分析における4つのP
それでは、4Pと呼ばれるProduct(プロダクト:製品)・Price(プライス:価格)・Place(プレイス:流通)・Promotion(プロモーション:販売促進)それぞれのポイントを解説します。すでにご存知の方は、本項は飛ばしていただいても構いません。
Product(プロダクト:製品)
企業の利益の源泉となる製品を考えます。品質・デザイン・ブランド名・パッケージ・サービス・保証までを含めて製品と考えますが、その根本には、「製品を通して顧客ニーズをどう満たすか」「製品を通して提供できるメリットは何か」という観点があります。
そのうえで、自社の製品を既存の市場の中でどう位置付けるかも重要になり、これには次項の価格も大きく関わってきます。
Price(プライス:価格)
市場で販売するうえでの価格です。価格を設定することで必然的に決定されてしまうものが、ターゲット層です。価格を決定する過程では、「顧客が購入してくれる価格なのか」「製品価値との整合性はあるか」「適正な利益を得られる価格であるか」ということの慎重な検討が不可欠となります。
そして、価格によって定まったターゲット層に確実に製品を届けるためには、「どのような形で製品を市場に流通させるのか」ということが鍵を握ります。
Place(プレイス:流通)
製品を市場に流通させるための流通経路や販売する場所が含まれます。実存店舗であれば、自社店舗・コンビニ・百貨店など形態は多岐にわたりますし、立地や店舗数も勘案する必要があります。また、近年規模が拡大しているネット通販のように、受注から販売までをインターネット上で完結させる方法も存在します。
いずれにせよ、「ターゲット層に確実に製品を届けることができる流通形態になっているのか」という観点でその妥当性を検証する必要があります。
また、どのような経路で販売するかということは、その製品のイメージ戦略にもつながります。コンビニでいつでも購入できる商品と、百貨店でしか取り扱いがない商品では、同じ商品であったとしても、その製品に対して顧客がもつイメージは大きく異なるでしょう。
Promotion(プロモーション:販売促進)
市場の顧客ニーズを満たす製品を製作し、ターゲット層を決め、そのターゲット層に購入機会を提供できる流通・販売経路を確保する。この後で、更に必要になることが、「いかに製品を認知してもらうか」ということです。
製品がどれほど優れていても認知されていなければ意味はありませんし、認知してもらったうえで、更に購入してもらえなければ企業に利益は生じません。
代表的な例としては広告やCMがありますが、この他にイベントの実施やメルマガの送付などもプロモーションのひとつの手法となります。
また、流通の検討と同様に、プロモーションに関しても「情報を確実にターゲット層に届ける」という観点から、発信メディアや市場に流す情報、そしてプロモーションにかける予算を検討する必要があります。
マーケティング担当が直面する4P分析の課題
4Pのうち1つの要素を考えただけで、4P分析を活用できているとはいえないでしょう。Product(プロダクト:製品)とPrice(プライス:価格)など相互に関連する4Pのうち複数の要素を掛け合うことで、初めて4P分析が効果を発揮するのです。このとき、「製品内容に対して価格は妥当性がある値段か」など各要素間で整合性がとられていることも重要となります。
企業のマーケティング担当者では企業のマーケティング担当者の業務範囲ではプロモーション以外の3つのPに対して施策をうてないケースも多く見受けられます。このように価格や製品仕様の決定が異なる部署で行われており相互の調整がなされない場合、一貫した戦略をとることが難しくなり、4P分析が形骸化する可能性もあります。
マーケティング・ミックスにおける4P・4C分析とは?
5分で学べるケーススタディ3選
ここからは実際に4P分析の活用で実績を残している製品やサービスを検証しながら、その成功の秘訣に迫っていきたいと思います。なお、それぞれの事例の特徴的なPについて書いていますが、実際に4P分析を行う際には、それぞれの分析の深さに違いはあってでも、4Pすべての分析は必要です。
・H&M Product×Price×Place
ZARAやForever21などと共に、ファストファッションを牽引するブランドのひとつにH&Mが存在します。H&Mは全世界に展開し年間売上は約3兆円を誇り、日本においても北海道から沖縄まで全国に店舗を構えています。H&Mの成功の理由は、製品の明確なコンセプトと流通形態にあります。
H&Mが目指した製品のコンセプトは、「高級ブランド製品の類似品を低価格で提供する」というものでした。これは従来、価格を理由に高級ブランド製品を手にすることができなかった層に対して、代替品を提供することでそのニーズを満たすことができます。
また、製品を他ブランドの類似品と定めてしまうことによって、自社でトレンドを生み出す必要やデザイン検討に割く予算を削減することで製造コストを抑えることが可能になり、低価格での製品提供が実現できるのです。
加えて、その製品を製作コストの安い世界中の工場で生産し、更に安価な海運で輸送するという生産・流通のシステムも低価格の実現、ひいてはH&M成功の重要な要因とっています。
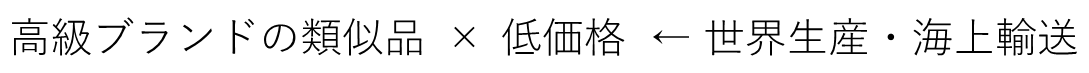
・ライザップ Product×Promotion
続いて、近年急速に発展し、今やトレーニングジムの代表格といっても過言ではないポジションを確立した「ライザップ」の事例です。
従来のトレーニングジムといえば、プールやランニングマシンといった設備などの、言わばトレーニングのための“場”を提供する事業形態が主でした。そこに着目したライザップは、「トレーナーのマンツーマン指導の下での筋力トレーニングや厳しい食事管理」という新たな形を打ち出し、「自分一人では甘えてしまう」「今までダイエットに挑戦したが失敗した」という多くに人のもつ悩みに訴えることに成功したのです。
また、ライザップが成長した要因として、サービスの内容もさることながら、優れたプロモーションがあったことも事実です。「ブーチ、ブーチ」という重低音と共にうつむき気味な小太りの人の映像が流れたかと思ったら、同じ人が次のシーンでは明るいメロディーと共に劇的に変化した体型で笑顔を見せるおなじみのCMは、数多くのパロディが作られるほどの反響を呼び、知名度の向上に大きく貢献しました。また、CMのモデルにタレントの赤井英和さんや経済アナリストの森永卓郎さんといった有名人を起用したことで、サービスに対する信頼度を向上させることにも成功しました。
トレーナーのマンツーマン指導と食事管理という新しくもニーズに適したProduct(プロダクト:製品)を「ビフォア・アフター」CMという優れたPromotion(プロモーション:販売促進)で広めたことが、ライザップの3年間で売上100億円という驚異的な成功を導いたのです。
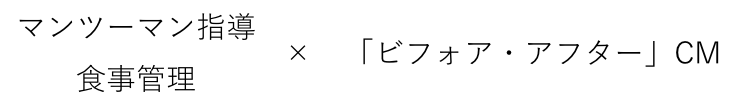
・「TRAIN SUITE(トランスイート)四季島」Product×Price
東日本旅客鉄道(JR東日本)が2017年5月に運行を開始した「TRAIN SUITE(トランスイート)四季島」は、乗車すること自体が旅の目的となるクルーズタイプの旅を提供する豪華寝台列車として注目を浴びており、旅行代金が2名1室の場合32万円~95万円とかなり高額であるにも関わらず、2017年5月~2018年3月出発分の応募件数は、通期の平均倍率の5.0倍となるほどの人気を誇っています。
「四季島」の成功の要因はどこにあるのでしょうか。
「四季島」が新たに提案する旅行というのは、今まで移動の手段に過ぎなかった列車に、「上質な空間やサービス、そして時間を提供する」という新たな価値を付与したものです。車内はフェラーリのデザインに携わった奥山清行氏によるプロデュースの高級感あふれる内装、食事も「四季島」専用に用意されたものが提供され、従来の列車旅行とは一線を画すものとなっています。
これは、従来の旅行に物足りなさを感じていた層に対して全く新しい形態の旅行スタイルを提案すると共に、その高額な価格も相まって「四季島」という新たなブランドを確立できたことが成功の要因といえるでしょう。
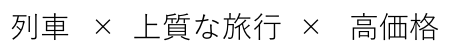
4Pと対になる「4C」
4Pの対になるマーケティングの別のフレームワークとして、「4C」というものも存在します。4Cは、次の4つの要素で構成されます。
- Customer Value(顧客にとっての価値)
- Customer Cost(顧客が費やすお金)
- Communication(顧客とのコミュニケーション)
- Convenience(顧客にとっての利便性)
4Pが企業の視点で、4Cが顧客(消費者)の視点で、という違いがあり4Pと4Cでマーケティングプランを組み立てることができます。
関連記事:4P理論と4C理論で組み立てるマーケティングプラン
マーケティング・ミックスにおける4P・4C分析とは?
まとめ
企業のマーケティング担当者が必ず一度は目にする4P分析。今回はマーケティング担当者の実践を想定し、4P分析の前ステップから直面する課題、3つの事例をご紹介しました。
ただし、4Pと4Cでマーケティングプランをいきなり立てるのではなく、「4P分析の前ステップ」の項で記載した、具体的なターゲットと自社のポジションをしっかりと設定することが重要です。これを怠るとプランも曖昧なものになってしまいます。
フレームワークを活用して、各要素を分析し、企業・顧客ともに利益を享受できるマーケティングプランを立てましょう。
イノーバでは、これらのフレームワークを含むBtoBマーケティングに課題や悩みを抱える方へ、伴走型マーケティング支援サービスを提供しております。よろしければご覧ください。



